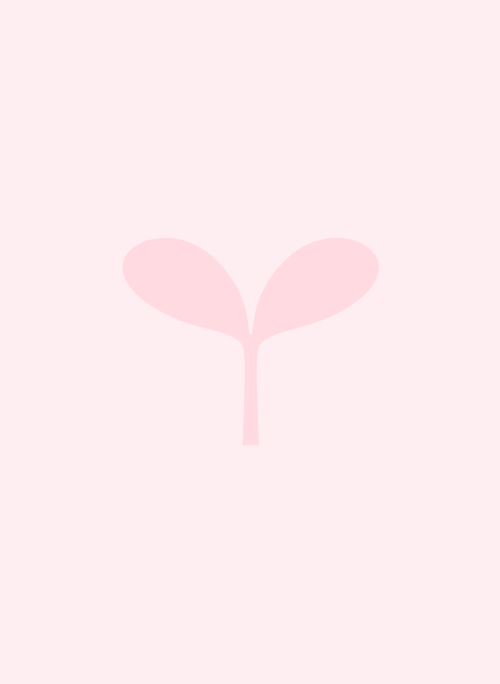真っ直ぐに僕はそのお店に向かう。扉を開け、カウンターにいたマスターと目が合うと、ホット珈琲を注文して、窓際の席に座った。
アンティーク。
こう言ってしまえば聞えは良い。しかし、木目を前面に出した店内のインテリアは、使い古され、その時間と共に艶やかな味が出ていると言うよりは、むしろ大いに黒染んでいる。
僕が座っているテーブルの辺りは、朝なのに薄暗く、ランプでともしたような雰囲気を作っていて、外の不純物が交わる雑然さと、建物の無機質さから完全に遮断された、言い換えれば別世界を演出していた。
あれ!?
珈琲が来るのを待っていた時、僕はコンビニエンスストアで買った雑誌が、無くなっていることに気が付いた。
きっと、バスの中にでも忘れてきたのだろう。
小脇に抱えたまま、眠ってしまって、その時にするりと落としてしまったのだろうか。
あの、顔面に迫ってくる柔肌のイメージは、今でも鮮明に脳裏に焼き付いていたし、僕は忘れられる筈もない。
既に読み古したとは言え、正直なところ、まだ、手放したくはなかった。
珈琲が運ばれる。
テーブルの端から、スライドするように、白く細い手で珈琲皿は背中を押され、僕の前に移動する。小さな金属製の容器に入ったクリームは、その傍らに慎ましく置かれた。
僕はクリームを滑らかに垂らし、珈琲の表面に渦巻きをつくる。
芳ばしい香りが、僕の周りを漂っている。
アンティーク。
こう言ってしまえば聞えは良い。しかし、木目を前面に出した店内のインテリアは、使い古され、その時間と共に艶やかな味が出ていると言うよりは、むしろ大いに黒染んでいる。
僕が座っているテーブルの辺りは、朝なのに薄暗く、ランプでともしたような雰囲気を作っていて、外の不純物が交わる雑然さと、建物の無機質さから完全に遮断された、言い換えれば別世界を演出していた。
あれ!?
珈琲が来るのを待っていた時、僕はコンビニエンスストアで買った雑誌が、無くなっていることに気が付いた。
きっと、バスの中にでも忘れてきたのだろう。
小脇に抱えたまま、眠ってしまって、その時にするりと落としてしまったのだろうか。
あの、顔面に迫ってくる柔肌のイメージは、今でも鮮明に脳裏に焼き付いていたし、僕は忘れられる筈もない。
既に読み古したとは言え、正直なところ、まだ、手放したくはなかった。
珈琲が運ばれる。
テーブルの端から、スライドするように、白く細い手で珈琲皿は背中を押され、僕の前に移動する。小さな金属製の容器に入ったクリームは、その傍らに慎ましく置かれた。
僕はクリームを滑らかに垂らし、珈琲の表面に渦巻きをつくる。
芳ばしい香りが、僕の周りを漂っている。