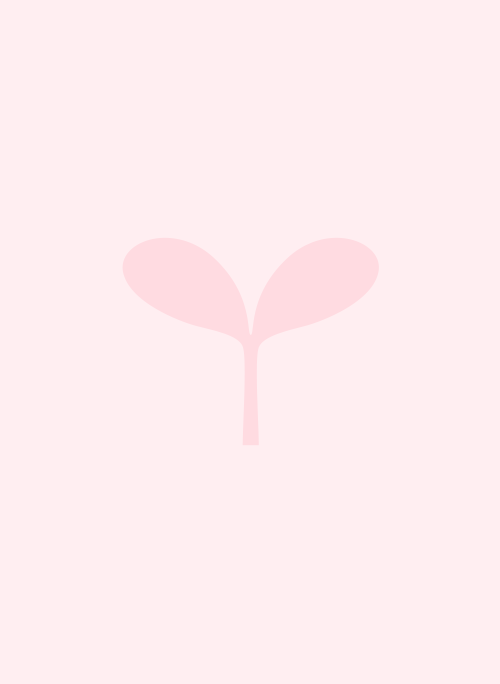「何でラーメン屋で、そんな大切な話をするの?」
怒ったようで、すねているような、それでも、頭の中で懸命に整理して理解しようとしている、そんな口調だった。
「ココへ連れてきたのは、珠子じゃないか」
「そうだけど……」
珠子も僕も、そこで言葉に詰まってしまった。今は沈黙が耐えられなかったのだが、珠子の方も同じような心境だったのかもしれない。
二人とも目の前のラーメンをすすって、平らげた。何色のスープで、どんな味がしたのかなどより、舌の感触だけを頼りに、ただ食べる、という作業を繰り返したようなものだった。
「さぁ、花束を買いに行こう」
「どこへ?」
条件反射のように、返事が返ってきた。珠子はまだ、ラーメンを食べ終わってはいない。人によっては残してしまうかもしれない量だが、珠子は気にしていないようだった。
「花屋」
「この辺、ないよ」
「そうなの」
「でも、あそこならあるかも……」
「あそこ?」
「そう、そんなに遠くないわ」
「ああ、なるほど。花束の代わりに、僕が連れて行ってあげるよ」
どうやら珠子とは、殆んど言葉を交わさずとも、意識を共有しているようだった。ぶっきらぼうな僕たちの会話の中で、彼女の言うあそこは、僕のいうあそこと、当たり前のように重なり合った。
怒ったようで、すねているような、それでも、頭の中で懸命に整理して理解しようとしている、そんな口調だった。
「ココへ連れてきたのは、珠子じゃないか」
「そうだけど……」
珠子も僕も、そこで言葉に詰まってしまった。今は沈黙が耐えられなかったのだが、珠子の方も同じような心境だったのかもしれない。
二人とも目の前のラーメンをすすって、平らげた。何色のスープで、どんな味がしたのかなどより、舌の感触だけを頼りに、ただ食べる、という作業を繰り返したようなものだった。
「さぁ、花束を買いに行こう」
「どこへ?」
条件反射のように、返事が返ってきた。珠子はまだ、ラーメンを食べ終わってはいない。人によっては残してしまうかもしれない量だが、珠子は気にしていないようだった。
「花屋」
「この辺、ないよ」
「そうなの」
「でも、あそこならあるかも……」
「あそこ?」
「そう、そんなに遠くないわ」
「ああ、なるほど。花束の代わりに、僕が連れて行ってあげるよ」
どうやら珠子とは、殆んど言葉を交わさずとも、意識を共有しているようだった。ぶっきらぼうな僕たちの会話の中で、彼女の言うあそこは、僕のいうあそこと、当たり前のように重なり合った。