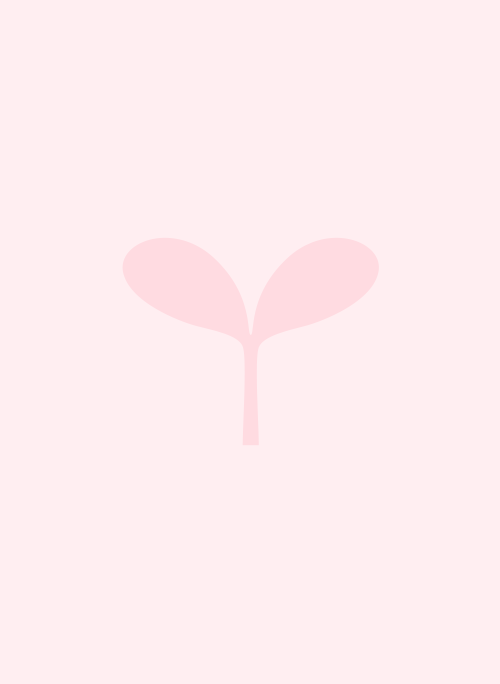高校に入学して、君のいない日々を過ごす。
何事も無かったかの様に振舞っても、時折、無性に寂しくなることがあった。
一歩先に外の世界に飛び込んだ君が、羨ましくもあり、妬ましくもある。
その一歩が踏み出せない僕は、本当に情けない男だった。
僕はある日、そのポスターを引き剥がした。
それは、もう必要ないと、自分自身に言い聞かせたかったから。
僕は変わらなければいけない。だから、受け入れたのだ。
突然、僕の未来は、水の中で広がる墨汁の中で過ごすような、黒い雲に覆われ、黒い海になった。何も見えない。それでも、自分の手で切り開いてゆかなければならないと思った。光という光は、僕が探さない限り、現れてはくれないのだ。
頭の中で、彼女の存在が大きく占めた時、声が聞こえるようになった。空気の振動を肌で感じることはない。
それは、彼女の声だけでなく、色々なポスターから発せられる自分への言葉。
全て、女性の声だった。
その声は自分の意思とは無関係に注がれる。場所を選ばず、時を選ばずに。
能力、と言えば語弊がある。授かったものとはとても思えない。
自然に身に付いたこの声を、僕は自分の意識でかき消す日々を送った。
何事も無かったかの様に振舞っても、時折、無性に寂しくなることがあった。
一歩先に外の世界に飛び込んだ君が、羨ましくもあり、妬ましくもある。
その一歩が踏み出せない僕は、本当に情けない男だった。
僕はある日、そのポスターを引き剥がした。
それは、もう必要ないと、自分自身に言い聞かせたかったから。
僕は変わらなければいけない。だから、受け入れたのだ。
突然、僕の未来は、水の中で広がる墨汁の中で過ごすような、黒い雲に覆われ、黒い海になった。何も見えない。それでも、自分の手で切り開いてゆかなければならないと思った。光という光は、僕が探さない限り、現れてはくれないのだ。
頭の中で、彼女の存在が大きく占めた時、声が聞こえるようになった。空気の振動を肌で感じることはない。
それは、彼女の声だけでなく、色々なポスターから発せられる自分への言葉。
全て、女性の声だった。
その声は自分の意思とは無関係に注がれる。場所を選ばず、時を選ばずに。
能力、と言えば語弊がある。授かったものとはとても思えない。
自然に身に付いたこの声を、僕は自分の意識でかき消す日々を送った。