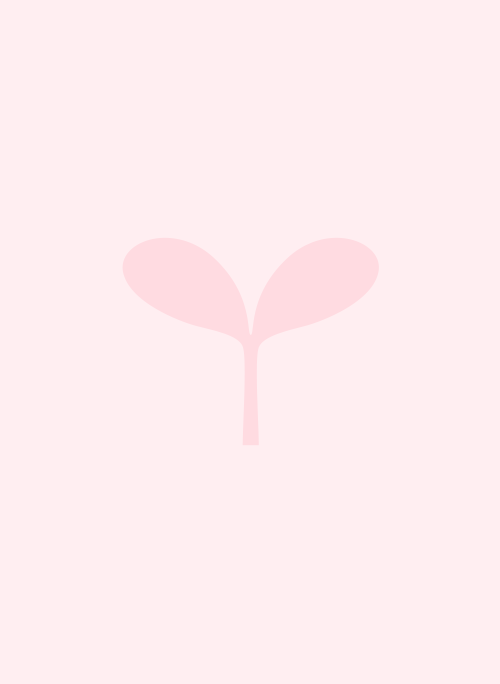「……ごめん」
ひと呼吸おいて、そう、言うしかなった。
今の僕には、それしか言えない。
「素直に謝られると、次の言葉が言えないじゃない」
珠子が腰から手を離し、今度は腕を組む。
「仕方ないわね。折角だし、このままデートする?」
明らかに自分が生きてきた世界とは違うノリだ。僕はどんな顔をしていいのか、わからない。
「彼女とかいないんでしょ? 『どうせ』とかは言わないけど。全然、興味無さそうだし」
「その格好で街を歩くのか?」
歩き出そうとする珠子を止める。ヒツコイようだが、メイド服なのだ。僕に言わせればコスプレだ。
「別にいいじゃない。よく似た格好が普段着だ、なんていう子もいるんだから」
「しかし……」
「本当は着たいんでしょ?」
僕が泡を食っていると、珠子に右手を握られ、引っ張られた。いや、引き寄せられたと言った方が適切だ。
「いろいろと、白状してもらうからね?」
珠子は更ににじり寄ると、右の眉毛をクイッとあげて、念を押すように、僕の瞳の中まで覗き込む。
そういえば、珠子は体の小さい僕の手を、ずっと離さず引いてくれた記憶がある。
柔らかくて、温かい手。
僕たちが手を繋いでいたのは、ずっと昔、幼い頃の話。なのに感触を覚えている。
珠子は何一つ変わっていない、僕はそう思った。
ひと呼吸おいて、そう、言うしかなった。
今の僕には、それしか言えない。
「素直に謝られると、次の言葉が言えないじゃない」
珠子が腰から手を離し、今度は腕を組む。
「仕方ないわね。折角だし、このままデートする?」
明らかに自分が生きてきた世界とは違うノリだ。僕はどんな顔をしていいのか、わからない。
「彼女とかいないんでしょ? 『どうせ』とかは言わないけど。全然、興味無さそうだし」
「その格好で街を歩くのか?」
歩き出そうとする珠子を止める。ヒツコイようだが、メイド服なのだ。僕に言わせればコスプレだ。
「別にいいじゃない。よく似た格好が普段着だ、なんていう子もいるんだから」
「しかし……」
「本当は着たいんでしょ?」
僕が泡を食っていると、珠子に右手を握られ、引っ張られた。いや、引き寄せられたと言った方が適切だ。
「いろいろと、白状してもらうからね?」
珠子は更ににじり寄ると、右の眉毛をクイッとあげて、念を押すように、僕の瞳の中まで覗き込む。
そういえば、珠子は体の小さい僕の手を、ずっと離さず引いてくれた記憶がある。
柔らかくて、温かい手。
僕たちが手を繋いでいたのは、ずっと昔、幼い頃の話。なのに感触を覚えている。
珠子は何一つ変わっていない、僕はそう思った。