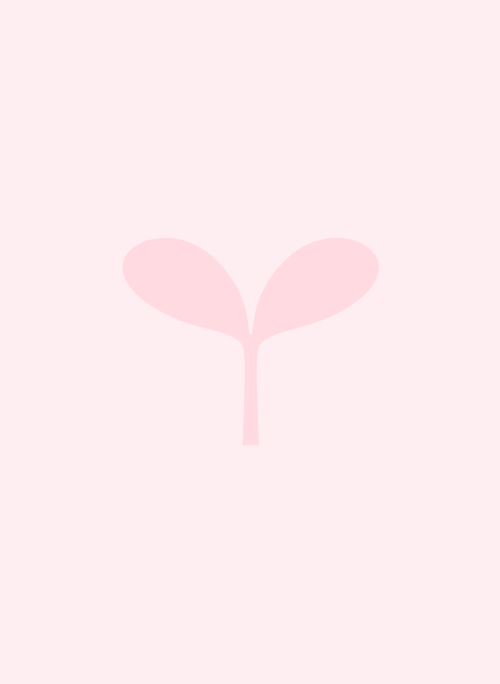幸恵さんは、早苗先生の相手の男性に、姉の元に戻ってほしいと頼んだのだそうだ。
でも、幸恵さんは強くは言えなかった。
籍を入れていなかった事もあったが、それが理由ではなく、相手の男性が酷く憔悴していたからだそうで、幸恵さんが知っている人相より、十年は年老いて見えたという。
それに二人が寄り添っていた頃、少なくとも姉が幸せそうに見えたのも、強く言えない大きな理由だった。
「ごめんなさいね。初対面なのに私ったら、玄関先でぺらぺらと喋っちゃって……」
「いいえ」
早苗先生の横で、幸恵の取り繕う表情をみて、僕は胸が痛くなった。
「さあ、姉さん。明るいお部屋に戻りましょう。お体に障るわ」
「幸恵さん、この方、誰よ? 誰の話をしているの?」
早苗先生は、僕を指差している。曲がった指は関節が浮き上がって、付け根から細かく震えていた。
幸恵さんは、早苗先生を誘い、抱きかかえるように奥の部屋に連れて行く。
「何かお手伝いしましょうか?」
「大丈夫。姉がこうなったのも、私が一因なんですから。これぐらい、平気」
踏ん張ったような幸恵の返事が僕を遮った。二人は廊下から部屋に入り、見えなくなった。
「よいっ、しょ」
立ち上がる際、思わず出た声だろうか。すぐに幸恵が戻ってくる。小鳥のブローチが傾いていた。
「あのう……」
「はい」
「このままじゃ、おばさんの方も参ってしまいますよ」
時が固まる。返事を貰うのに、少し時間がかかった。
「やっぱり、そうよね。でも、姉を置いては行けないから……」
でも、幸恵さんは強くは言えなかった。
籍を入れていなかった事もあったが、それが理由ではなく、相手の男性が酷く憔悴していたからだそうで、幸恵さんが知っている人相より、十年は年老いて見えたという。
それに二人が寄り添っていた頃、少なくとも姉が幸せそうに見えたのも、強く言えない大きな理由だった。
「ごめんなさいね。初対面なのに私ったら、玄関先でぺらぺらと喋っちゃって……」
「いいえ」
早苗先生の横で、幸恵の取り繕う表情をみて、僕は胸が痛くなった。
「さあ、姉さん。明るいお部屋に戻りましょう。お体に障るわ」
「幸恵さん、この方、誰よ? 誰の話をしているの?」
早苗先生は、僕を指差している。曲がった指は関節が浮き上がって、付け根から細かく震えていた。
幸恵さんは、早苗先生を誘い、抱きかかえるように奥の部屋に連れて行く。
「何かお手伝いしましょうか?」
「大丈夫。姉がこうなったのも、私が一因なんですから。これぐらい、平気」
踏ん張ったような幸恵の返事が僕を遮った。二人は廊下から部屋に入り、見えなくなった。
「よいっ、しょ」
立ち上がる際、思わず出た声だろうか。すぐに幸恵が戻ってくる。小鳥のブローチが傾いていた。
「あのう……」
「はい」
「このままじゃ、おばさんの方も参ってしまいますよ」
時が固まる。返事を貰うのに、少し時間がかかった。
「やっぱり、そうよね。でも、姉を置いては行けないから……」