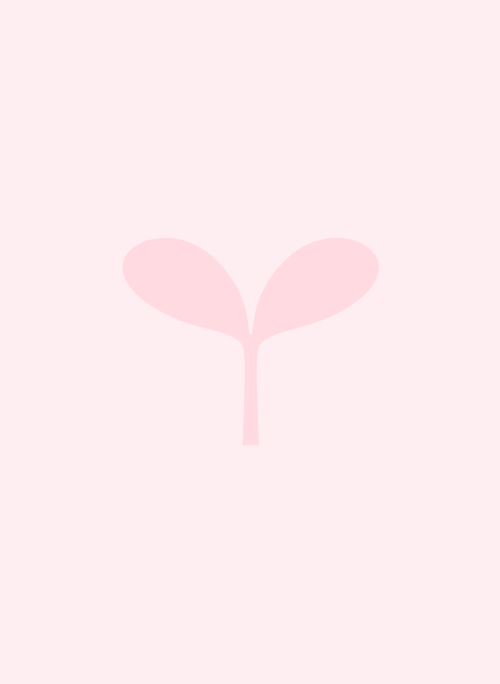幸恵は膝を詰めて座り込み、早苗先生の両手を握って、必死に話し掛けている。
そもそも、僕のことなど、覚えているかどうかも分らないのに、幸恵は何度も何度も僕を知っているのかと早苗先生に問い掛けている。
やがて、反応のなくなった早苗先生の手を、幸恵は丁寧に膝の上に置くと、力なく自分の手を戻した。
「ごめんなさい。もしかしたら、と思って」
幸恵は僕に振り向いて、首に巻いていたスカーフを、肩から抜いた。
「ごめんなさい」
幸恵は重ねて言った。
「早苗先生は……」
そう言い掛けて、僕は言葉に詰まった。
幸恵の落胆した様子が、僕の声を奪った。
「上井さん、と仰いましたね? わざわざお越し頂き、ありがとうございます」
非常に上品で、軟らかい声だった。早苗のそれとは、また違う。
「一年前から急に物覚えが悪くなりましてね。姉を説得してお医者様に診て頂いたところ、手術でどうにかなるものではないそうで。私たちは双子なんですけどね、両親が残してくれたこんな大きな家にたった二人で暮らしていているのですが、今になっては、姉は双子の妹である私ですら、分らない事もあるんです」
僕はじっと、幸恵の言葉を噛み締めた。いや、そうするしかなかった。
外の世界に出て、目的地で僕が見たものは、病に侵された恩師の姿……。それが、僕が手に入れた紛れもない現実だった。
そもそも、僕のことなど、覚えているかどうかも分らないのに、幸恵は何度も何度も僕を知っているのかと早苗先生に問い掛けている。
やがて、反応のなくなった早苗先生の手を、幸恵は丁寧に膝の上に置くと、力なく自分の手を戻した。
「ごめんなさい。もしかしたら、と思って」
幸恵は僕に振り向いて、首に巻いていたスカーフを、肩から抜いた。
「ごめんなさい」
幸恵は重ねて言った。
「早苗先生は……」
そう言い掛けて、僕は言葉に詰まった。
幸恵の落胆した様子が、僕の声を奪った。
「上井さん、と仰いましたね? わざわざお越し頂き、ありがとうございます」
非常に上品で、軟らかい声だった。早苗のそれとは、また違う。
「一年前から急に物覚えが悪くなりましてね。姉を説得してお医者様に診て頂いたところ、手術でどうにかなるものではないそうで。私たちは双子なんですけどね、両親が残してくれたこんな大きな家にたった二人で暮らしていているのですが、今になっては、姉は双子の妹である私ですら、分らない事もあるんです」
僕はじっと、幸恵の言葉を噛み締めた。いや、そうするしかなかった。
外の世界に出て、目的地で僕が見たものは、病に侵された恩師の姿……。それが、僕が手に入れた紛れもない現実だった。