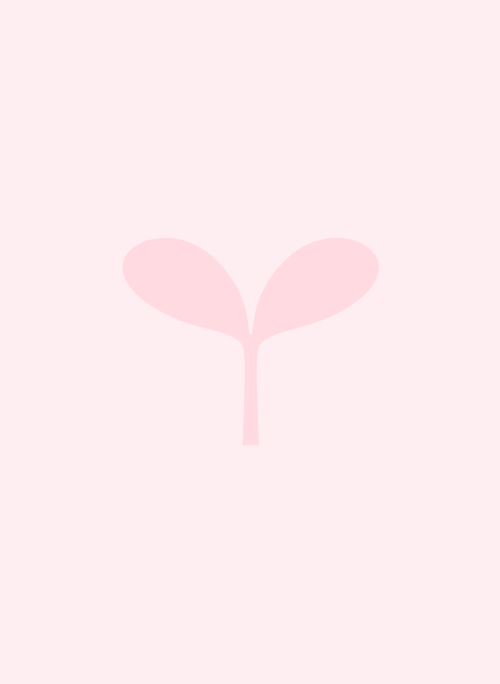「こんにちは」
ふいに右側から声を掛けられ、僕はしどろもどろした。
「せっ、先生?」
先生と同じ声だ。
とっさに振り向くと、早苗先生と同じ顔の女性が、廊下に立っていた。
若葉色のスーツを着ている。左胸には小鳥のブローチ。首には白いスカーフを巻いている。
しかし、先生とは僅かに違う。一見して同じに見えるが、相槌を打ってくれている先生よりも、断然、垢抜けている。
「小岩井早苗の妹の幸恵です。姉に訪ねていらしたんですね?」
僕は頭の中を掻きむしり、懸命に整理した。状況を理解するには、相手に聞くしかなかった。
「ええ、そうです」
「幸恵さん、この方は何しにお越しになったんですか?」
それは、突然のことだった。
早苗先生が不思議そうな顔をして、僕を指差し、そう言った。口元の皺が露になり、縮んでは伸びる。
「貴方はどなたですか? 誰なんですか?」
今度は僕の方に、首を傾(かし)げて聞く。真ん丸く見開いた瞳は、明ら様に僕の姿を取り込んでいた。
「姉さん、分りませんか? 教育実習生の頃の生徒さんが、わざわざ訪ねてきてくれたのですよ」
幸恵が顔をこわばらせて、確認するように、もう一度僕を見つめ、そして早苗先生の顔を覗き込む。
僕はその時、そのやりとりを眺める、傍観者の一人となり下がった。
ただ、直感に基づいて丹念にその意味を考える程、残念という言葉を通り越し、頭の中が真っ白になってゆく。
悲しくて、悲しくて、ぽろぽろと涙の粒が溢れた。頬を伝って転げ落ちるそれらは生温かく、正直なところ、僕には痒かった。
ふいに右側から声を掛けられ、僕はしどろもどろした。
「せっ、先生?」
先生と同じ声だ。
とっさに振り向くと、早苗先生と同じ顔の女性が、廊下に立っていた。
若葉色のスーツを着ている。左胸には小鳥のブローチ。首には白いスカーフを巻いている。
しかし、先生とは僅かに違う。一見して同じに見えるが、相槌を打ってくれている先生よりも、断然、垢抜けている。
「小岩井早苗の妹の幸恵です。姉に訪ねていらしたんですね?」
僕は頭の中を掻きむしり、懸命に整理した。状況を理解するには、相手に聞くしかなかった。
「ええ、そうです」
「幸恵さん、この方は何しにお越しになったんですか?」
それは、突然のことだった。
早苗先生が不思議そうな顔をして、僕を指差し、そう言った。口元の皺が露になり、縮んでは伸びる。
「貴方はどなたですか? 誰なんですか?」
今度は僕の方に、首を傾(かし)げて聞く。真ん丸く見開いた瞳は、明ら様に僕の姿を取り込んでいた。
「姉さん、分りませんか? 教育実習生の頃の生徒さんが、わざわざ訪ねてきてくれたのですよ」
幸恵が顔をこわばらせて、確認するように、もう一度僕を見つめ、そして早苗先生の顔を覗き込む。
僕はその時、そのやりとりを眺める、傍観者の一人となり下がった。
ただ、直感に基づいて丹念にその意味を考える程、残念という言葉を通り越し、頭の中が真っ白になってゆく。
悲しくて、悲しくて、ぽろぽろと涙の粒が溢れた。頬を伝って転げ落ちるそれらは生温かく、正直なところ、僕には痒かった。