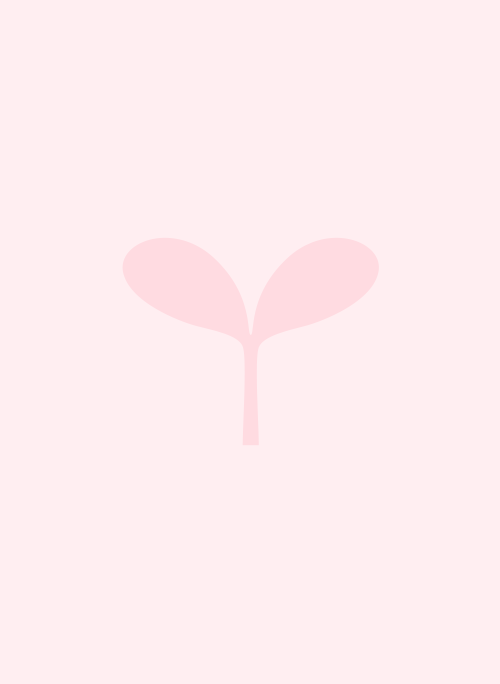駅に着く寸前、小さな粘土がひとつ、頭に命中したように感じた。
考える暇もなく、次が当たる。そして、次。
ぼたぼたと脳天に命中する度に顎が揺れ、強制的に頷く。
一気に降り出した雨だった。地面に叩きつけられるような強烈な雨によって、みるみるうちに視界が曇る。
もう少しで駅の屋根に滑り込めたというのに、僕はずぶ濡れになった。思わず立ち竦んだ後、そこから水溜まりを蹴って、屋根の下まで走った。
重い……。惨めな姿になって、最初に浮かんだ言葉だった。
気を取り直して自動券売機まで真っ直ぐに進み、濡れた指先でお金を入れた。無言で切符を買い、改札機を通る。走った直後でもあり、僕の呼吸は未だに荒かった。酸素ボンベから吸入されているように、いちいち音を発する。
ホームの階段を上ったと同時に、電車が進入してきた。うまい具合いに目の前で扉の前で停車し、ようやく濡れた衣服に気がまわった。
最後の階段の一段を上るように、電車に乗る。たった二駅先が、僕の目的地だった。
動き出した見慣れない都会の風景を、扉越しに眺める。
今思えばそう華やかでもない街があっという間に過ぎ、どす黒くそして所々赤く錆付いた工場の殺風景な連なりを見て、僕は呼吸をそれなりに整える。
人の姿は見えない。建物に完全に囲まれた公園に、ぽつんと設置された真っ赤なベンチと滑り台が、ペンキの塗りたてのように映え、暗号のように景色から浮き出ていた。
やがて、大きな橋に差し掛かり、川が広がる。川の水は煌めきのない金色で、クリームを入れ過ぎた珈琲にも見えた。
きっと、川底など見える筈がない、と僕は最初から思っていた。透明に生まれた川の流れも、その純粋さと引き替えに、必ず濁ってゆくのだ。
眼球に映る景色の全てが、脳の中に取り込まれ、変換される。
いったいどこまでの情報が、僕の記憶に取り込まれるのだろうか?
僕の呼吸は、完全に正常に戻り、濡れて少し重くなった衣服を、手触りで確認した。
考える暇もなく、次が当たる。そして、次。
ぼたぼたと脳天に命中する度に顎が揺れ、強制的に頷く。
一気に降り出した雨だった。地面に叩きつけられるような強烈な雨によって、みるみるうちに視界が曇る。
もう少しで駅の屋根に滑り込めたというのに、僕はずぶ濡れになった。思わず立ち竦んだ後、そこから水溜まりを蹴って、屋根の下まで走った。
重い……。惨めな姿になって、最初に浮かんだ言葉だった。
気を取り直して自動券売機まで真っ直ぐに進み、濡れた指先でお金を入れた。無言で切符を買い、改札機を通る。走った直後でもあり、僕の呼吸は未だに荒かった。酸素ボンベから吸入されているように、いちいち音を発する。
ホームの階段を上ったと同時に、電車が進入してきた。うまい具合いに目の前で扉の前で停車し、ようやく濡れた衣服に気がまわった。
最後の階段の一段を上るように、電車に乗る。たった二駅先が、僕の目的地だった。
動き出した見慣れない都会の風景を、扉越しに眺める。
今思えばそう華やかでもない街があっという間に過ぎ、どす黒くそして所々赤く錆付いた工場の殺風景な連なりを見て、僕は呼吸をそれなりに整える。
人の姿は見えない。建物に完全に囲まれた公園に、ぽつんと設置された真っ赤なベンチと滑り台が、ペンキの塗りたてのように映え、暗号のように景色から浮き出ていた。
やがて、大きな橋に差し掛かり、川が広がる。川の水は煌めきのない金色で、クリームを入れ過ぎた珈琲にも見えた。
きっと、川底など見える筈がない、と僕は最初から思っていた。透明に生まれた川の流れも、その純粋さと引き替えに、必ず濁ってゆくのだ。
眼球に映る景色の全てが、脳の中に取り込まれ、変換される。
いったいどこまでの情報が、僕の記憶に取り込まれるのだろうか?
僕の呼吸は、完全に正常に戻り、濡れて少し重くなった衣服を、手触りで確認した。