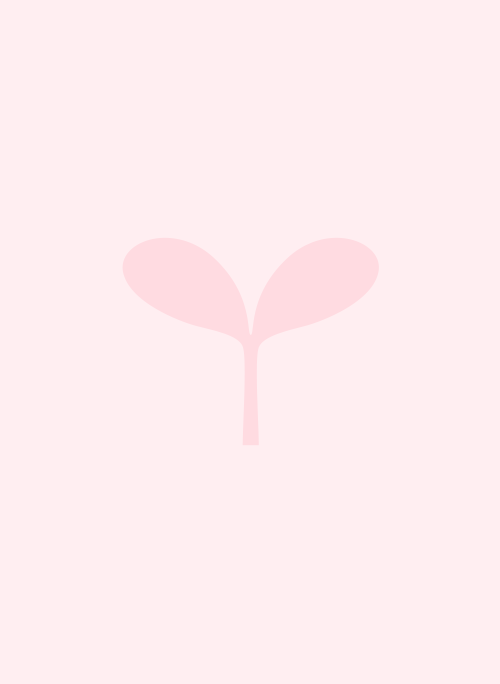今の状態を正直に話した僕に対するマスターの条件は、唯一つ。
それは、実家に僕の居場所を知らせることだった。
そのことについて、僕が両親に連絡をするのではなく、マスターから話をするとのことで、正直、そこまで甘えてしまっても良いのか判断に迷っていたところ、珠子が話の流れに乗って、僕が住むところもないと口添えすると、マスターは見つかるまでこの店で寝てもいい、と言ってくれた。
「朝はココ、冷えるんですよ。珠子、上井君に毛布を貸してあげなさい」
珠子は僕とマスターの間に、陣取っている。思い当たる毛布があったらしく、うんうんと頷いた。
こうして、僕は明日から、この店で働くことになった。いや、そればかりか、眠る場所まで得ることが出来た。
奇遇か偶然か。旨過ぎる話だが、幸運だったと言わざるをえない。
ただ、どことなく珠子のはしゃぎ方が異常で、何やら胡散臭さを感じたが、今は何も言うまいと決めた。
「すみません。何から何まで……。宜しくお願いします」
「こちらこそ。同じ郷里の若い方が店を手伝ってくれるなんて、嬉しいですよ」
マスターの言葉の真意が、分かるような気がした。
外に出てきて一番苦労したのは、そういうことだったのかと。僕はここまでやってきた不安感を、もう一度辿りながら、なんとなく納得出来た。
それは、実家に僕の居場所を知らせることだった。
そのことについて、僕が両親に連絡をするのではなく、マスターから話をするとのことで、正直、そこまで甘えてしまっても良いのか判断に迷っていたところ、珠子が話の流れに乗って、僕が住むところもないと口添えすると、マスターは見つかるまでこの店で寝てもいい、と言ってくれた。
「朝はココ、冷えるんですよ。珠子、上井君に毛布を貸してあげなさい」
珠子は僕とマスターの間に、陣取っている。思い当たる毛布があったらしく、うんうんと頷いた。
こうして、僕は明日から、この店で働くことになった。いや、そればかりか、眠る場所まで得ることが出来た。
奇遇か偶然か。旨過ぎる話だが、幸運だったと言わざるをえない。
ただ、どことなく珠子のはしゃぎ方が異常で、何やら胡散臭さを感じたが、今は何も言うまいと決めた。
「すみません。何から何まで……。宜しくお願いします」
「こちらこそ。同じ郷里の若い方が店を手伝ってくれるなんて、嬉しいですよ」
マスターの言葉の真意が、分かるような気がした。
外に出てきて一番苦労したのは、そういうことだったのかと。僕はここまでやってきた不安感を、もう一度辿りながら、なんとなく納得出来た。