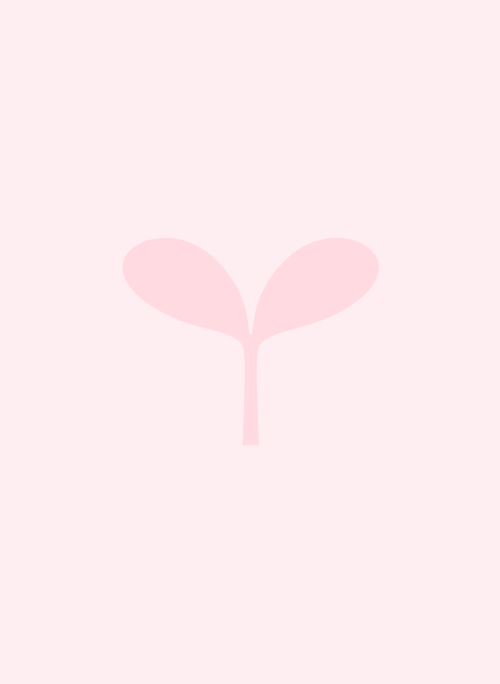僕はそこから100メートル先のバスの停留所まで堅く口を閉じて歩き、スポットライトに照らされながらも、寂しそうに1台だけぽつんと止まっていた大型バスを、遠巻きに見付ける。
赤地に白いストライプのバスは、磨きたてというより、寧ろ新品のピカビカと言える状態であり、それ自身があたかも発光しているようで、更にその周辺まで輝いて見えた。
僕は今から、この高速バスに乗って故郷を出るのだ。
故郷を……出る。
そう、故郷を出て行かなければならない。そうでなければ、何も始まらないし、始まりはしないだろう。
無地の白いTシャツに、穴が開いて、色の落ちた青白いジーンズ。
決して小さくもないくすんだオレンジ色のリュックサックを一つ背負い、後ろのポケットにむりやり突っ込んだ財布の他に、僕が持っているものなど何も無かった。
僕の家はお寺だった。
伝統と由緒のある寺に対し、父は僕が継いでくれるものだと、生まれた時から当たり前のように考えていた。
何の疑問も感じない父と、何も言わなかった僕。
長い年月を経て、高校を卒業する頃になって、ようやく僕は自分の本心を話した。
この町を、出たい。
そう一言、父にこぼすと、父は何が起こったのか理解も出来ずに、先代が使用していた奥の間に引き篭もった。母はその場で肩を落とし、ただ、ただ泣いた。
このまま片田舎で、人生を全うする気は、毛頭なかった。
僕には僕の世界がある。
そして、自由がある。
お寺をバカにしているんじゃない。そういう話ではないのだ。
両親には、結局上手く話せなかった。誤解をしているのなら解いておきたかったが、二人ともそういう雰囲気ではなかった。
──その話をした後、深夜の停留所から出発する高速バスのチケットを、急いで買いに行った。まとめてあった荷物を、リュックサックに詰める前に行動した。
本当のところ、その時の僕は、ただ単純に、外の世界に出たかったのかもしれない。
色々な想いが頭の中で錯綜していたが、行動を起こすことで、今は掻き消してしまいたかった。
赤地に白いストライプのバスは、磨きたてというより、寧ろ新品のピカビカと言える状態であり、それ自身があたかも発光しているようで、更にその周辺まで輝いて見えた。
僕は今から、この高速バスに乗って故郷を出るのだ。
故郷を……出る。
そう、故郷を出て行かなければならない。そうでなければ、何も始まらないし、始まりはしないだろう。
無地の白いTシャツに、穴が開いて、色の落ちた青白いジーンズ。
決して小さくもないくすんだオレンジ色のリュックサックを一つ背負い、後ろのポケットにむりやり突っ込んだ財布の他に、僕が持っているものなど何も無かった。
僕の家はお寺だった。
伝統と由緒のある寺に対し、父は僕が継いでくれるものだと、生まれた時から当たり前のように考えていた。
何の疑問も感じない父と、何も言わなかった僕。
長い年月を経て、高校を卒業する頃になって、ようやく僕は自分の本心を話した。
この町を、出たい。
そう一言、父にこぼすと、父は何が起こったのか理解も出来ずに、先代が使用していた奥の間に引き篭もった。母はその場で肩を落とし、ただ、ただ泣いた。
このまま片田舎で、人生を全うする気は、毛頭なかった。
僕には僕の世界がある。
そして、自由がある。
お寺をバカにしているんじゃない。そういう話ではないのだ。
両親には、結局上手く話せなかった。誤解をしているのなら解いておきたかったが、二人ともそういう雰囲気ではなかった。
──その話をした後、深夜の停留所から出発する高速バスのチケットを、急いで買いに行った。まとめてあった荷物を、リュックサックに詰める前に行動した。
本当のところ、その時の僕は、ただ単純に、外の世界に出たかったのかもしれない。
色々な想いが頭の中で錯綜していたが、行動を起こすことで、今は掻き消してしまいたかった。