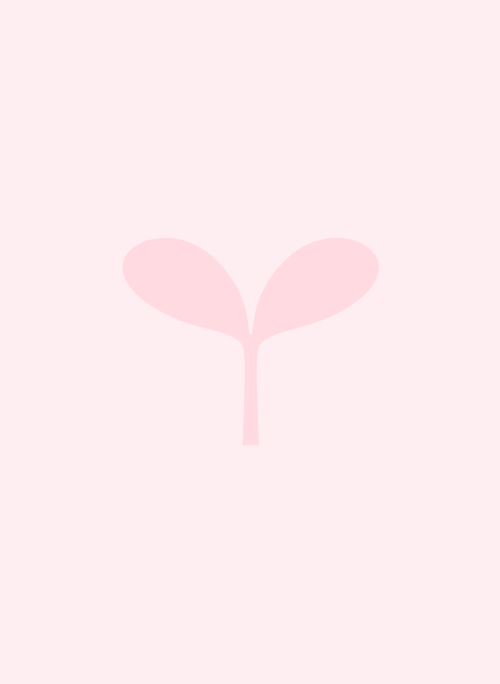「じゃあ、久し振りだよね?」
確かめるように、繰り返して言ってしまった。不思議な感じがしたので、僕自身が時間を欲しがった。
「ほんとに、……そうね。久し振りよね」
興奮しているのではなくて、しみじみという珠子。話を合わせている風にも聞こえる。
「いや、そういう意味ではなくって、何でこの店にフラフラとやって来たんだろうってね、考えていた。それが鮎川のいる店っていうのも……」
彼女の名字は鮎川という。鮎川珠子がフルネームだ。
「名字で呼ばれるのって、私、何か調子狂うし気持ち悪い。それに……カミイ君のその答えが、奇遇って言葉なんじゃないの?」
「珠子の方こそ、下の名前で呼んでないクセに。それと……それが奇遇だってことは分かっているんだけど、どこかしっくりしなくってさ」
珠子が「ふーん」と言った後、ほんの数秒間だと思うが、僕は訳の分からない孤立感を味わった。手に入れたばかりの安心感が、急激に不安感へと変貌してゆく。
「ねえ、私、今日、六時でアガリなの。ごはん食べにいかない?」
珠子の言葉が、血管に注ぎ込まれる。急速に体の細胞に浸透し、手首の辺りまでヒンヤリと広がった。心臓の動きをも、止める冷たさだ。
「悪いけど、一緒には行けないよ。今日は行くところがあるんだ」
僕は決まっていたセリフ回しのように、自分なりに答えた。
うまく息が出来ない。
「どこ?」
「言わないよ」
それ以上話すと、酸素が無くなってしまいそうだ。新鮮な空気が、どうしても吸えない。赤血球に何かが詰まっているようだ。
「それじゃ、住所教えて」
「住所? 無いよ」
そう言い終わると、僕は息を吸うために、溜め込んでいた空気を吐いた。ボンベの酸素が吸えず、潜水の初心者のようなことを、仕出かしていたのだ。
「無い? 無いってどういう意味よ」
「だって、家をコッソリ出て来たんだ」
耳が熱くなった。僕はそう言いつつ、彼女に目を合わせなかった。
確かめるように、繰り返して言ってしまった。不思議な感じがしたので、僕自身が時間を欲しがった。
「ほんとに、……そうね。久し振りよね」
興奮しているのではなくて、しみじみという珠子。話を合わせている風にも聞こえる。
「いや、そういう意味ではなくって、何でこの店にフラフラとやって来たんだろうってね、考えていた。それが鮎川のいる店っていうのも……」
彼女の名字は鮎川という。鮎川珠子がフルネームだ。
「名字で呼ばれるのって、私、何か調子狂うし気持ち悪い。それに……カミイ君のその答えが、奇遇って言葉なんじゃないの?」
「珠子の方こそ、下の名前で呼んでないクセに。それと……それが奇遇だってことは分かっているんだけど、どこかしっくりしなくってさ」
珠子が「ふーん」と言った後、ほんの数秒間だと思うが、僕は訳の分からない孤立感を味わった。手に入れたばかりの安心感が、急激に不安感へと変貌してゆく。
「ねえ、私、今日、六時でアガリなの。ごはん食べにいかない?」
珠子の言葉が、血管に注ぎ込まれる。急速に体の細胞に浸透し、手首の辺りまでヒンヤリと広がった。心臓の動きをも、止める冷たさだ。
「悪いけど、一緒には行けないよ。今日は行くところがあるんだ」
僕は決まっていたセリフ回しのように、自分なりに答えた。
うまく息が出来ない。
「どこ?」
「言わないよ」
それ以上話すと、酸素が無くなってしまいそうだ。新鮮な空気が、どうしても吸えない。赤血球に何かが詰まっているようだ。
「それじゃ、住所教えて」
「住所? 無いよ」
そう言い終わると、僕は息を吸うために、溜め込んでいた空気を吐いた。ボンベの酸素が吸えず、潜水の初心者のようなことを、仕出かしていたのだ。
「無い? 無いってどういう意味よ」
「だって、家をコッソリ出て来たんだ」
耳が熱くなった。僕はそう言いつつ、彼女に目を合わせなかった。