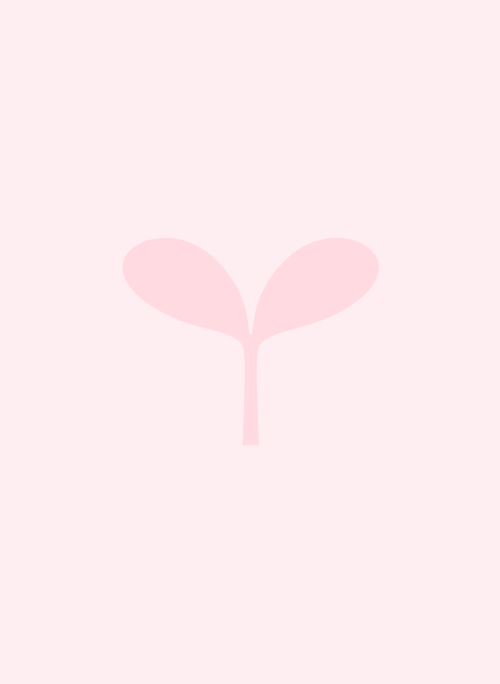「そう、珠子よ!」
僕のちっぽけだった世界の色が、一気に明るく変わった。体の中を支配していた何もかもが、ゴツゴツとした大きな両の手で鷲掴みにされ、網脂に包まれていたかのように、きれいに毟り取られた。
彼女は、幼馴染みの珠子だった。
僕の近所に住んでいて、中学まで一緒だった同級生。
知らない街に出てきて、思い掛けず珠子に遭遇した。一人で強がっていても、結局は一人ぼっちな訳で、僕は心底不安だったのだと、改めて思い知らされた。
「ものすごくオッサン臭い顔で、しかも胡散臭そうな目で私を見るから、ちょっと心配になったよ」
笑顔のすぐ横に、不満という文字が見え隠れする。しかし、反対側には優しさという文字が、恥ずかしそうに覗いていた。
「奇遇だよ。本当に奇遇だね」
突然の出来事に、愛着の無かった喫茶店が、自分の寛げる空間に衣替えする。僕は久し振りに、穏やかな気分に浸った。もはや、テーブルの艷を眺めることすら、心地好い。
「そうみたいね。うんうん」
珠子は一度溜め息を付いた後、両手を腰に当てて、胸を張った。上がっていた眉毛が、面白いぐらいに下がった。
「どころでさ、なんでこの街にいるの?」
珈琲を口に含んで、飲み込み際に珠子が聞く。
「なんで? 引っ越したじゃない。私」
そうだった。
高校入学時に、珠子は引っ越したのだった。
僕のちっぽけだった世界の色が、一気に明るく変わった。体の中を支配していた何もかもが、ゴツゴツとした大きな両の手で鷲掴みにされ、網脂に包まれていたかのように、きれいに毟り取られた。
彼女は、幼馴染みの珠子だった。
僕の近所に住んでいて、中学まで一緒だった同級生。
知らない街に出てきて、思い掛けず珠子に遭遇した。一人で強がっていても、結局は一人ぼっちな訳で、僕は心底不安だったのだと、改めて思い知らされた。
「ものすごくオッサン臭い顔で、しかも胡散臭そうな目で私を見るから、ちょっと心配になったよ」
笑顔のすぐ横に、不満という文字が見え隠れする。しかし、反対側には優しさという文字が、恥ずかしそうに覗いていた。
「奇遇だよ。本当に奇遇だね」
突然の出来事に、愛着の無かった喫茶店が、自分の寛げる空間に衣替えする。僕は久し振りに、穏やかな気分に浸った。もはや、テーブルの艷を眺めることすら、心地好い。
「そうみたいね。うんうん」
珠子は一度溜め息を付いた後、両手を腰に当てて、胸を張った。上がっていた眉毛が、面白いぐらいに下がった。
「どころでさ、なんでこの街にいるの?」
珈琲を口に含んで、飲み込み際に珠子が聞く。
「なんで? 引っ越したじゃない。私」
そうだった。
高校入学時に、珠子は引っ越したのだった。