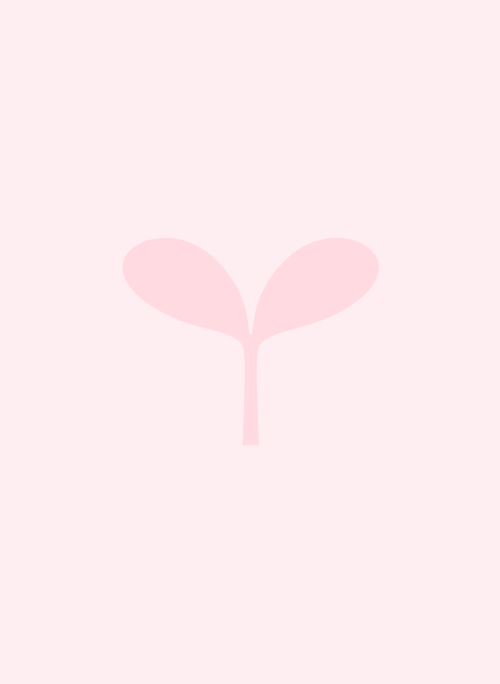サナエ先生の最後の実習日に合わせて、クラスで秘かに名簿を作った。
みんなで出し合ったお金で作った、サナエ先生のクラスアルバム。
簡素な緑色のボール紙で作った表紙に、簡素な名簿のコピー。クラス全員が揃って撮った写真を貼り付け、それぞれの思いを綴った文章。ステープラーで閉じられた他愛のないものだったが、それでも、全員分の冊数が完成した時の級友たちの弾けるような笑顔と、透き通った歓声が、忘れられない。
それほどサナエ先生に対する冷たさが、僕たちの故郷にはあった。
サナエ先生がクラス全員からそれを受け取った時、「嬉しくて、嬉しくて。もう涙が止まりません」と、顔をくしゃくしゃにして泣いた。
僕の涙もサナエ先生の言葉通り、いつまでも止まらなかった。
その時、僕たちは確かにそのイメージの全てを、大人たちに邪魔されないよう、僕たちだけの心の中に仕舞い込んだのだと思う。
◇
僕はそこに書かれていたサナエ先生の住所を、家を飛び出す夜になって、急いで書き写した。
それは、突然そんな時期のことを、一度布団に入って浅い眠りに付き、そこから込み上げるように、鮮明に思い出してしまったからだ。
裸足のまま、夜の寒さに身を置き、電気も付けずに押入れの中からアルバムを探し出す。ダンボール箱の隙間に挟まっていたアルバムを引き抜くと、緑色の表紙に何本もの、丸め損なって折れたようなシワが出来ていた。
僕は窓際からぼんやりと差し込んだ月明かりの中で、しかし、そのシワを見て、逆に安心したように力が抜けた。
短い間であったが、サナエ先生を恩師と言って差し支えなかった。
まだ、そこに書かれていた住所に住んでおられるのなら、是非、お目に掛り、ご挨拶をしたい。
自分のことを、覚えておられるかどうかは分からない。自信もない。
でも、お礼が言いたかった。
これから、未知の都会で頑張ってみることを、僕は早苗先生に報告したかった。
みんなで出し合ったお金で作った、サナエ先生のクラスアルバム。
簡素な緑色のボール紙で作った表紙に、簡素な名簿のコピー。クラス全員が揃って撮った写真を貼り付け、それぞれの思いを綴った文章。ステープラーで閉じられた他愛のないものだったが、それでも、全員分の冊数が完成した時の級友たちの弾けるような笑顔と、透き通った歓声が、忘れられない。
それほどサナエ先生に対する冷たさが、僕たちの故郷にはあった。
サナエ先生がクラス全員からそれを受け取った時、「嬉しくて、嬉しくて。もう涙が止まりません」と、顔をくしゃくしゃにして泣いた。
僕の涙もサナエ先生の言葉通り、いつまでも止まらなかった。
その時、僕たちは確かにそのイメージの全てを、大人たちに邪魔されないよう、僕たちだけの心の中に仕舞い込んだのだと思う。
◇
僕はそこに書かれていたサナエ先生の住所を、家を飛び出す夜になって、急いで書き写した。
それは、突然そんな時期のことを、一度布団に入って浅い眠りに付き、そこから込み上げるように、鮮明に思い出してしまったからだ。
裸足のまま、夜の寒さに身を置き、電気も付けずに押入れの中からアルバムを探し出す。ダンボール箱の隙間に挟まっていたアルバムを引き抜くと、緑色の表紙に何本もの、丸め損なって折れたようなシワが出来ていた。
僕は窓際からぼんやりと差し込んだ月明かりの中で、しかし、そのシワを見て、逆に安心したように力が抜けた。
短い間であったが、サナエ先生を恩師と言って差し支えなかった。
まだ、そこに書かれていた住所に住んでおられるのなら、是非、お目に掛り、ご挨拶をしたい。
自分のことを、覚えておられるかどうかは分からない。自信もない。
でも、お礼が言いたかった。
これから、未知の都会で頑張ってみることを、僕は早苗先生に報告したかった。