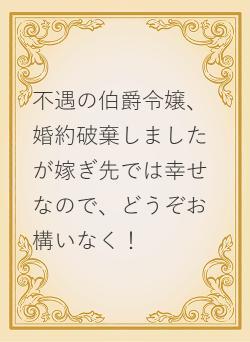そんな最前線の様子を魔法で見つめていたのは、後方部隊で待機中の魔法師団のアルヴィートとセリである。
因みにこちらは物理も魔法も効かない無敵と言える障壁魔法で護られている。
もちろんこんな有り得ないだろをやってのけるのは、たぶんこの大陸で勝てる者なしの魔法師セリである。
しかも、それは身を守る様にイソルガ義兄にアマリア姉上2人にもかけている。
それは彼らが王族とその伴侶の2人だからである。
半端なく強い2人だが、億万が一が無いとは言えないための処置である。
本当に必要なのかはセリにも甚だ疑問であるが、兄王に頼まれれば仕方ない。
なんだかんだ兄王は弟妹に甘く優しい。
「セリ、とうとう我慢ならずにイソルガ義兄さんが突っ込んでいくよ?」
それを聞いてセリは、すこし動き出す。
「捕虜の治療準備しておこう」
そう言うなり、魔法で治療用テントを整え始めた。
「セリ? それ必要?」
呑気な様子でアルヴィートが聞いてくるのに、セリは整ったテントを見つつ答える。
「多分一番情報持ってるのが半死半生レベルで連行されてくるよ? 姉上達は情報欲しいんだもの」
「んー、確かになぁ。セリは状況の読みが的確だね。じゃあ拘束魔法出来るのが必要! だな?」
「そうね、どっちも出来なくはないけど負荷は少ない方が助かるな。うっかりしかねないし」
兄妹は緊張感などかけらも見せないままに、話し合うと部下を呼ぶ。
「そうだな。おーい、レミー!!」
「はい、副団長」
「レミーはセリに付いててくれ。捕虜が来たら拘束魔法頼むな」
「承知いたしました。ではこれより、セリ様のお側に付かせて頂きます」
部下からの返事に、ようやくセリは微笑みを見せる。
「うん、よろしくね。頼りにしてるわ、レミー」
「レミーは拘束魔法や防御魔法。あとサポート系が得意な魔法師だから助かるわ」
頬を少し赤くして照れつつレミーは、しっかりと言葉を返す
「セリ様に、そのようにお褒めにあずかり光栄です」
笑顔が可愛い美少女の見かけだが、レミーは御歳150を超える魔法師の先輩で生き字引なのだが性格はおっとり控えめなのだ。
魔法師は魔力のお陰で老化が緩やかだが、レミーのそれはなかなかに凄い。
この魔法師団で王族兄妹を抜いて、五本の指に入る魔力量の保持者だった。
因みにこちらは物理も魔法も効かない無敵と言える障壁魔法で護られている。
もちろんこんな有り得ないだろをやってのけるのは、たぶんこの大陸で勝てる者なしの魔法師セリである。
しかも、それは身を守る様にイソルガ義兄にアマリア姉上2人にもかけている。
それは彼らが王族とその伴侶の2人だからである。
半端なく強い2人だが、億万が一が無いとは言えないための処置である。
本当に必要なのかはセリにも甚だ疑問であるが、兄王に頼まれれば仕方ない。
なんだかんだ兄王は弟妹に甘く優しい。
「セリ、とうとう我慢ならずにイソルガ義兄さんが突っ込んでいくよ?」
それを聞いてセリは、すこし動き出す。
「捕虜の治療準備しておこう」
そう言うなり、魔法で治療用テントを整え始めた。
「セリ? それ必要?」
呑気な様子でアルヴィートが聞いてくるのに、セリは整ったテントを見つつ答える。
「多分一番情報持ってるのが半死半生レベルで連行されてくるよ? 姉上達は情報欲しいんだもの」
「んー、確かになぁ。セリは状況の読みが的確だね。じゃあ拘束魔法出来るのが必要! だな?」
「そうね、どっちも出来なくはないけど負荷は少ない方が助かるな。うっかりしかねないし」
兄妹は緊張感などかけらも見せないままに、話し合うと部下を呼ぶ。
「そうだな。おーい、レミー!!」
「はい、副団長」
「レミーはセリに付いててくれ。捕虜が来たら拘束魔法頼むな」
「承知いたしました。ではこれより、セリ様のお側に付かせて頂きます」
部下からの返事に、ようやくセリは微笑みを見せる。
「うん、よろしくね。頼りにしてるわ、レミー」
「レミーは拘束魔法や防御魔法。あとサポート系が得意な魔法師だから助かるわ」
頬を少し赤くして照れつつレミーは、しっかりと言葉を返す
「セリ様に、そのようにお褒めにあずかり光栄です」
笑顔が可愛い美少女の見かけだが、レミーは御歳150を超える魔法師の先輩で生き字引なのだが性格はおっとり控えめなのだ。
魔法師は魔力のお陰で老化が緩やかだが、レミーのそれはなかなかに凄い。
この魔法師団で王族兄妹を抜いて、五本の指に入る魔力量の保持者だった。