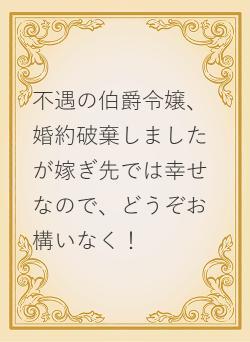「セリ、そっちの首尾はどうなってる?」
謁見の間のさらに奥の執務机に着いて書類と格闘している、一番上の兄にして国王陛下のジェラルド2世はそう声を掛けてやっと顔を上げた。
「こちらはいつでも出られる様に日々備えてるから問題ない。でも今回なぜわざわざラグーンに援軍要請したの?」
そこが疑問だった。
うちの魔法騎士団と魔法師団が合わされば間違いなく国境は守れる。
それでも竜騎士団を呼んだ訳はもしかして……
「お前の予測通りだよ。ラグーンとの結束を見せつけその上で完膚無きまでに叩き、こちら側までの侵略なんてアホのする事と教えるための援軍要請だ」
「それを言い出したのって……」
「アマンダとアルヴィートに決まってるだろう」
深い溜息とともに告げる兄の顔は苦り切っている。
「あの2人は好戦的だし、やられたら最低で3倍返しだから……」
兄の返事にポツリと呟けば
「はぁぁぁぁぁ……」
ものすごい深いため息が吐き出される。
あまりにもなそのため息に思わず言った。
「陛下、胃痛がするなら手当するけど?」
私の言葉に兄はむくっと顔を持ち上げると返事をした。
「いや、大丈夫だ。無事帰ってきた時には、スマンが頼むかもしれない……」
そんな痛々しい兄に、私はそっと差し出す。
「国王陛下、先にこっち渡しとくね」
そう言って差し出したのは、精神を落ち着ける調合をした私特製のキャンディー。
「うぅ……、セリ。お前とセイだけが頼りだよ」
この個性あふれる兄弟を見ながら国のトップとかつくづく大変だよなと思うといたたまれなくて、2人きりなのもあり気安くポンポンと肩を叩いた。
「アマンダ姉様とヴィー兄様は、今に始まったわけじゃないから仕方ないよね……」
「そうだな……」
遠い目をして胃のあたりを抑える兄が不憫で仕方ないセリだった。
かと言って絶対に代わりたくはないが。
そういう意味も含め、国のトップに立つ長兄にはセリは敬意と尊敬の念を持ち接しているのだった。
謁見の間のさらに奥の執務机に着いて書類と格闘している、一番上の兄にして国王陛下のジェラルド2世はそう声を掛けてやっと顔を上げた。
「こちらはいつでも出られる様に日々備えてるから問題ない。でも今回なぜわざわざラグーンに援軍要請したの?」
そこが疑問だった。
うちの魔法騎士団と魔法師団が合わされば間違いなく国境は守れる。
それでも竜騎士団を呼んだ訳はもしかして……
「お前の予測通りだよ。ラグーンとの結束を見せつけその上で完膚無きまでに叩き、こちら側までの侵略なんてアホのする事と教えるための援軍要請だ」
「それを言い出したのって……」
「アマンダとアルヴィートに決まってるだろう」
深い溜息とともに告げる兄の顔は苦り切っている。
「あの2人は好戦的だし、やられたら最低で3倍返しだから……」
兄の返事にポツリと呟けば
「はぁぁぁぁぁ……」
ものすごい深いため息が吐き出される。
あまりにもなそのため息に思わず言った。
「陛下、胃痛がするなら手当するけど?」
私の言葉に兄はむくっと顔を持ち上げると返事をした。
「いや、大丈夫だ。無事帰ってきた時には、スマンが頼むかもしれない……」
そんな痛々しい兄に、私はそっと差し出す。
「国王陛下、先にこっち渡しとくね」
そう言って差し出したのは、精神を落ち着ける調合をした私特製のキャンディー。
「うぅ……、セリ。お前とセイだけが頼りだよ」
この個性あふれる兄弟を見ながら国のトップとかつくづく大変だよなと思うといたたまれなくて、2人きりなのもあり気安くポンポンと肩を叩いた。
「アマンダ姉様とヴィー兄様は、今に始まったわけじゃないから仕方ないよね……」
「そうだな……」
遠い目をして胃のあたりを抑える兄が不憫で仕方ないセリだった。
かと言って絶対に代わりたくはないが。
そういう意味も含め、国のトップに立つ長兄にはセリは敬意と尊敬の念を持ち接しているのだった。