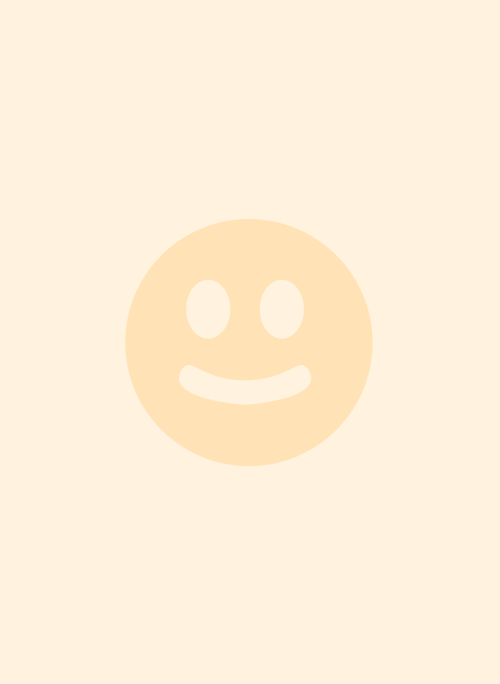どれだけこのままだったのか、よくわからない。
時計を見ると、六時を少し回ったころを指していたけれど、それが朝か夕方かも、よくわからない。
ただ、吐きそうになったから、身を起こしてトイレへ向かった。
そのかえり、また寝室へ行こうとしたときに、それが目に入ったのだ。
リビングの、レースのカーテンのすそに、見慣れた何かがしがみついていて、じっと動かずにいたのが見えた。
貴司にふられる前の日。
わたしは例の恒例行事を彼に見せるために、一匹のセミの幼虫を、朝のうちに採って来ていた。
ところが、仕事から帰ってきて見ると、その姿があったはずのバケツの中になく、どこを探しても見つからなかった。
なのでわたしは諦め、彼の誕生日当日にもう一度採りに行こうと思い、そのまま今まで忘れていたのだ。
それが、今になって見つかったというわけだ。
わたしがいつも見ていたセミの羽化は、とても神秘的で、まるで幻想の世界にいる心地さえ味わうほどであったというのに、今、カーテンにいるそれは、まるっきり違っていた。
それは今までみたどれよりも不格好で、薄気味悪く、茶ばんでいて、とてもみじめだった。
当然なのだ。
カーテンにへばりついたそれは、幼体から成体の頭を中途半端に出した状態で、――死んでいたのだから。
背は丸まっていて、まるで出来損ないの胎児みたいだった。
それは横から見ると、数字の『9』に、とてもよく似ていた。
わたしはレースにしっかりとしがみついているそれを手で崩さないようにして取った。
……軽かった。
まるで、命という中身が抜けてしまったぶん、厚みがなくなってしまったかのようだと思った。
手の平の上でそれを転がしながら眺めるうち、何故だか、可笑しくてたまらなくなり、ふふっと声を出して笑った。
この手の上の軽さが、なんだか、自分の今までの幻想を全て壊してしまいそうだというのに、笑うのを止められなかった。
わたしはそれをしばし続けて、それから飽きたようにゴミ箱に放り、浴室へ向かった。
おわり