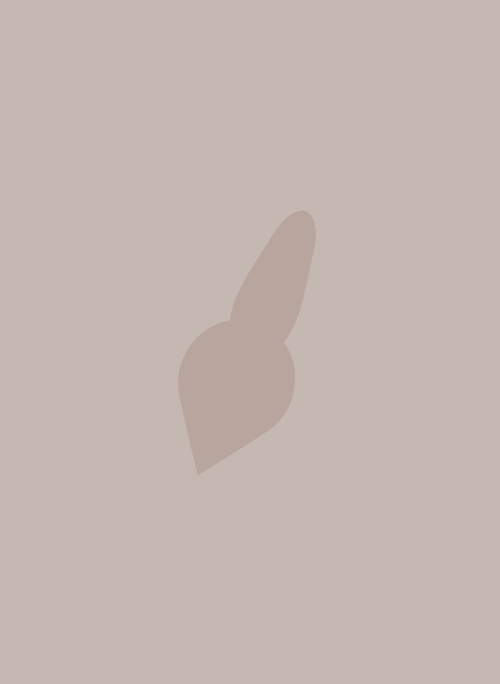「そうだったんですか?ありがとうございます!いつも聴いてくださって。それに…」
明音さんが少し照れたような顔をして、
「私、自分の声に自信がなかったんです。でも、あなたに声を好きだっていってもらえて、とってもうれしいです!ありがとうございます!」
と言って、嬉しそうにはにかんだ。
その表情をみた途端、俺は我慢できず、明音さんの両手を自分の手で握ってしまった。
「あの…俺!こうやって、あか、小林さんに会えるの最後かもしれないし、はじめまして会う人にこんなこと言われるのもなんだと思いますが、言わせてください!俺は、小林さんが…明音さんが好きです!」
「えっ?ち、ちょっと、なにいってるのよ、こんな公共の場で」
明音さんに恥ずかしそうに、てんぱりながらいわれて、ここが電車の中だということを思い出した。
「えっ、あっ、ご、ごめんなさい!」
真っ赤な顔でそういうと、
「ちょっと着いてきて」
と言われて、ちょうど到着した駅に明音さんは俺を手をひっぱりながら降りた。
明音さんが少し照れたような顔をして、
「私、自分の声に自信がなかったんです。でも、あなたに声を好きだっていってもらえて、とってもうれしいです!ありがとうございます!」
と言って、嬉しそうにはにかんだ。
その表情をみた途端、俺は我慢できず、明音さんの両手を自分の手で握ってしまった。
「あの…俺!こうやって、あか、小林さんに会えるの最後かもしれないし、はじめまして会う人にこんなこと言われるのもなんだと思いますが、言わせてください!俺は、小林さんが…明音さんが好きです!」
「えっ?ち、ちょっと、なにいってるのよ、こんな公共の場で」
明音さんに恥ずかしそうに、てんぱりながらいわれて、ここが電車の中だということを思い出した。
「えっ、あっ、ご、ごめんなさい!」
真っ赤な顔でそういうと、
「ちょっと着いてきて」
と言われて、ちょうど到着した駅に明音さんは俺を手をひっぱりながら降りた。