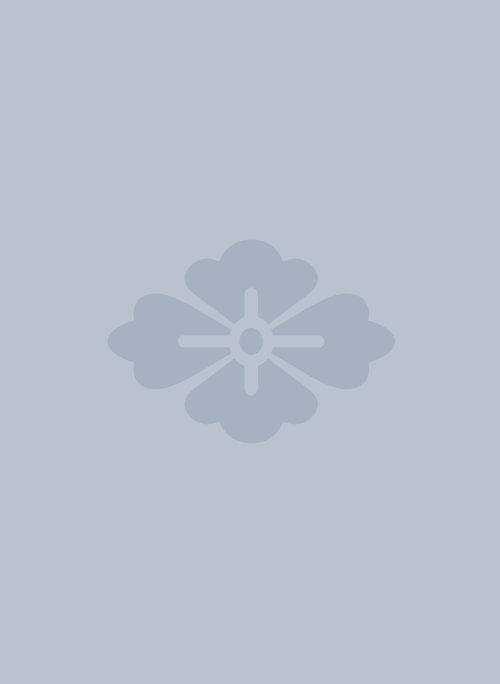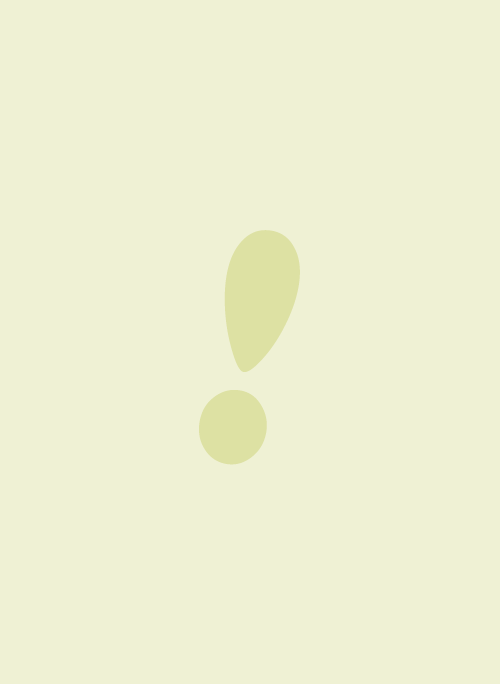耳を塞ぎたくなったが、
彼に演技がバレたことよりも
カケルが私の名前を呼んでくれなかったことに
少し、腹が立った。
なぜか今更
病院の独特なにおいで鼻が満たされていることに気づいた。
それは、カケルに嘘が発覚しても、
私はまだ、彼の中で綺麗な存在であるだろう
自信と余裕からだ。
「どうして記憶喪失のふりをしたんだ?
それで、俺が楽になるとでも思ったのか?」
頭は落ち着き払っていたが、
少し時間が経ってからこたえた。
その方が余情があって綺麗な私を演出できると思ったから。
「思ったよ。」
私は穏やかな声でそう言い、
カケルの三日月の形をした目をとらえた。
彼に演技がバレたことよりも
カケルが私の名前を呼んでくれなかったことに
少し、腹が立った。
なぜか今更
病院の独特なにおいで鼻が満たされていることに気づいた。
それは、カケルに嘘が発覚しても、
私はまだ、彼の中で綺麗な存在であるだろう
自信と余裕からだ。
「どうして記憶喪失のふりをしたんだ?
それで、俺が楽になるとでも思ったのか?」
頭は落ち着き払っていたが、
少し時間が経ってからこたえた。
その方が余情があって綺麗な私を演出できると思ったから。
「思ったよ。」
私は穏やかな声でそう言い、
カケルの三日月の形をした目をとらえた。