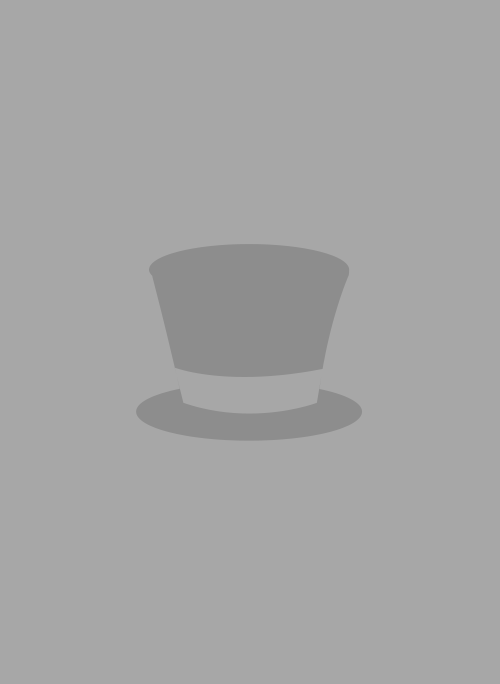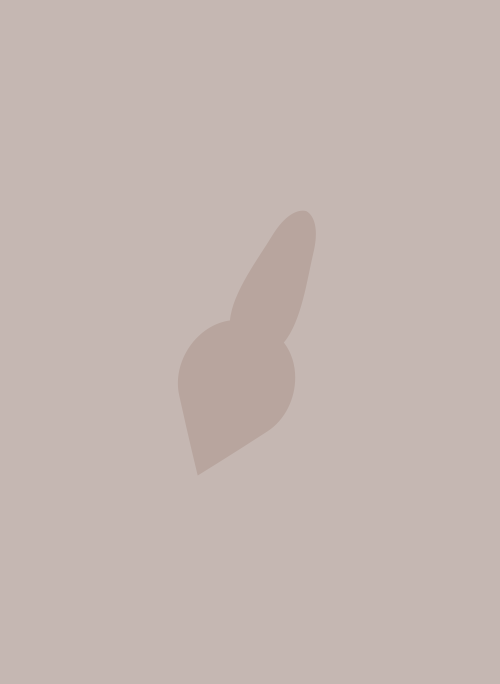「なにが始まったの?」
ゆっくりと、カヤノは僕に向かって歩いてくる。
足音は窓の外の雨音にかき消された。
家の中の静寂がかえって際立った。
「何が?それはあなたも解ってるはず……」
薄くグロスを塗った唇がゆっくり動く。
そこから視線を外せずにいる僕は、ソファに張り付いたまま動けない。
妖しい光を浮かべた瞳は真っ直ぐにこちらを見つめたまま。
ふわり、姉の香りが鼻を掠めた。
甘い甘い蜜のような、罠に誘う香り。
「姉さ……」
「名前で呼んでと言ったはずよ」
カヤノ―――。
僕が彼女の名前を口にするよりわずかに早く、カヤノの唇が僕のそれを塞いでいた。