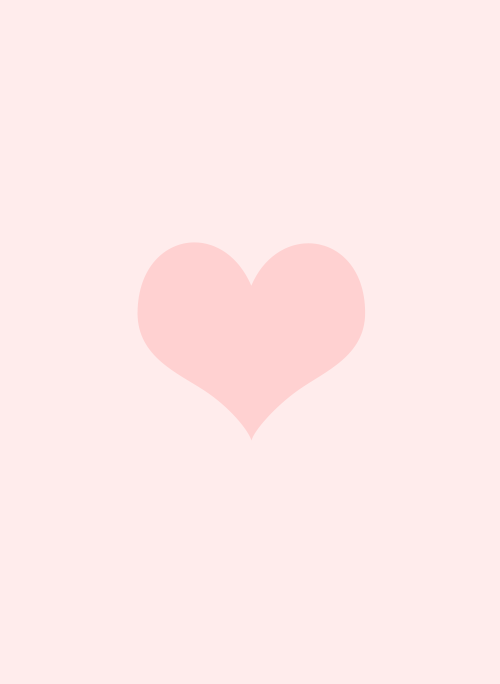横から視線を感じたので目を向けると、彼が変わらない無表情でじっと私を見ていた。
わかりやすく嬉しさを滲ませた会話を展開してしまった恥ずかしさから、つい過剰に目を逸らす。
そんな私の様子になんて気付かずに、大ちゃんは明るい声をかぶせる。
「千隼も一緒な」
彼の方は眼球を少し動かしただけだ。
「仕事忙しい。二人で行けば?」
大ちゃんと二人で行けるのだから断られてホッとしたはずなのに、なんだか拒絶されたようで喜べない。
「えー、じゃあ明日にする?菜乃、明日は?」
急いで予定の組み替えをする私が答える前に、彼は重ねて言った。
「俺はいいから。二人で行けって」
「二人じゃないよ。里奈も来るからさ」
私の期待はいつも吹き飛ぶほどの燃えカスになる。
わかっていたはずだったのに。
何も知らない大ちゃんはいつだって残酷だ。
こうなるとわかっていたら最初から断ったのに。
いや、わかっていても私に大ちゃんの誘いは断れないな。
結局、傷つく方傷つく方に、私は流されていくんだ。
里奈と大ちゃんを目の前に一人でいるのは辛い。
せめて、誰か他にいてくれたら。
せめて、この人が来てくれたらよかったのに。
恨めしい気持ちを含めてそっと見上げると、彼の方でもまばたき1回分私を見下ろしていた。
「やっぱり俺も行く」
何の前触れもなく彼がさっきの言葉を撤回した。
「あれ?仕事は?」
「大丈夫そうだから、行く」
淡々とした声にこれ以上質問を受け付ける余地は残されていない。
「わかった。じゃあ店と時間決めたら連絡する。菜乃と待ち合わせて来て」
「いや、現地集合でいい。じゃ、俺は仕事だから」
腕時計に目を落とす仕草につられて私も自分の時計を見ると、もう始業時間まで数分だった。
顔を上げた先に彼の姿はもうない。
「俺もそろそろ行く。菜乃、また夜な」
大ちゃんが残していった明るい笑顔の余韻を、もう誰もいない入り口を見つめて少しだけ味わう。
そして全てを振り払うように、勢いよくポットに熱湯を注いだ。