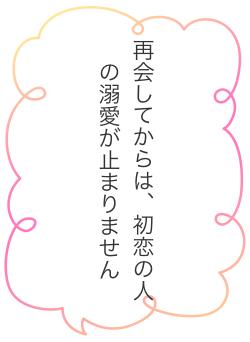その日以来、依人は学校で縁を見かける度に挨拶をするようになった。
始めはぎこちなく返してくれた縁だったが、衣替えが済んだ頃になると、次第にぎこちなさはなくなり、今では縁から挨拶をしてくれることが少しずつ増えていった。
六月のある日の昼休み、昼ご飯を買いに購買部に向かうと、並ぶ列の最後に縁がぼんやりと突っ立っているのを見かけた。
「佐藤さん、」
依人はすかさず縁の後ろをゲットすると、軽く肩を叩いて話しかけた。
「こんにちはっ、先輩」
縁は振り向くと照れながらにこりと破顔させた。
(癒されるな……可愛い)
縁の愛らしさを目の当たりにして、頬が緩みそうになる。
「まさかここで会うなんて思わなかったよ」
依人はよく購買で昼ご飯を買っていたが、これまで縁を見かけたことがなかったので、意外だと思った。
「今日は寝坊して、お弁当作れなかったんです」
「自分で作ってるの?」
料理が不得意な依人は、意外だと言いたげに目をぱちぱちと瞬きをして驚きを露わにした。
「はい……お母さんが仕事で忙しいので、家事全般はあたしの担当なんです」
「……勉強との両立は大変だね」
父親は? と言う疑問は喉まで出かかったが、すんでで飲み込んだ。
土足で踏み込む真似は失礼極まりないし、何より縁に無神経な男だと軽蔑されたくなかったのだ。
「慣れましたよ」
縁はなんてことないと言いたげに微笑んだ。
縁のその微笑から、健気な一面が垣間見えた気がした。
それぞれ昼ご飯を購入して、二人は途中まで肩を並べて教室棟へ向かう。
「あのっ」
階段を登る前に縁は依人に声をかけた。
「あの、今更なんですけど、今度球技大会の日のお礼させてくれませんか?」
「お礼?」
「はい、本当はすぐにでもしたかったんですが……あたしに出来ることならなんでも言ってください」
(男に“なんでもする”なんて言っちゃ駄目だって……)
良く言えば純粋無垢、悪く言うと無自覚かつ無防備。
依人はそんな縁の危うさに、嘆息しそうになった。
本当なら、危機感を持ってくれ、とたしなめたいが、縁はただ純粋に感謝しているだけなのだ。
「じゃあ、俺のお願い一つ聞いくれる?」
「はいっ、言ってください!」
依人が応えると、縁は瞳をきらきらと輝かせた。
依人は少し膝を折ると、縁の耳元にそっと顔を近付け、
「明日一緒にお昼食べてくれる?」
内緒話をするように囁いた。
始めはぎこちなく返してくれた縁だったが、衣替えが済んだ頃になると、次第にぎこちなさはなくなり、今では縁から挨拶をしてくれることが少しずつ増えていった。
六月のある日の昼休み、昼ご飯を買いに購買部に向かうと、並ぶ列の最後に縁がぼんやりと突っ立っているのを見かけた。
「佐藤さん、」
依人はすかさず縁の後ろをゲットすると、軽く肩を叩いて話しかけた。
「こんにちはっ、先輩」
縁は振り向くと照れながらにこりと破顔させた。
(癒されるな……可愛い)
縁の愛らしさを目の当たりにして、頬が緩みそうになる。
「まさかここで会うなんて思わなかったよ」
依人はよく購買で昼ご飯を買っていたが、これまで縁を見かけたことがなかったので、意外だと思った。
「今日は寝坊して、お弁当作れなかったんです」
「自分で作ってるの?」
料理が不得意な依人は、意外だと言いたげに目をぱちぱちと瞬きをして驚きを露わにした。
「はい……お母さんが仕事で忙しいので、家事全般はあたしの担当なんです」
「……勉強との両立は大変だね」
父親は? と言う疑問は喉まで出かかったが、すんでで飲み込んだ。
土足で踏み込む真似は失礼極まりないし、何より縁に無神経な男だと軽蔑されたくなかったのだ。
「慣れましたよ」
縁はなんてことないと言いたげに微笑んだ。
縁のその微笑から、健気な一面が垣間見えた気がした。
それぞれ昼ご飯を購入して、二人は途中まで肩を並べて教室棟へ向かう。
「あのっ」
階段を登る前に縁は依人に声をかけた。
「あの、今更なんですけど、今度球技大会の日のお礼させてくれませんか?」
「お礼?」
「はい、本当はすぐにでもしたかったんですが……あたしに出来ることならなんでも言ってください」
(男に“なんでもする”なんて言っちゃ駄目だって……)
良く言えば純粋無垢、悪く言うと無自覚かつ無防備。
依人はそんな縁の危うさに、嘆息しそうになった。
本当なら、危機感を持ってくれ、とたしなめたいが、縁はただ純粋に感謝しているだけなのだ。
「じゃあ、俺のお願い一つ聞いくれる?」
「はいっ、言ってください!」
依人が応えると、縁は瞳をきらきらと輝かせた。
依人は少し膝を折ると、縁の耳元にそっと顔を近付け、
「明日一緒にお昼食べてくれる?」
内緒話をするように囁いた。