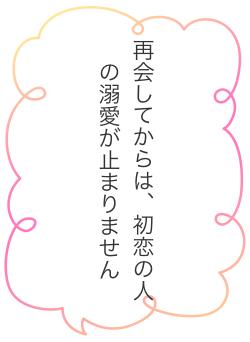肌荒れとは無縁なほど滑らかな雪のように白い肌、黒目がちの形の良い大きな瞳、瞳を縁どる長い睫毛、さくらんぼのように赤い小さな唇。
一言で言うと可憐な美少女。
依人は思わず息を呑んだ。
「……」
振り向いたきり固まったまま無言を貫く彼女。
見る見る内に頬は赤く染まりだした。
「足、怪我しているよね?」
「……は、い」
依人がもう一度尋ねると、我に返った彼女は無言のまま躊躇いがちに小さく頷いた。
その声はとても小さいものだったが、鈴を転がしたようなソプラノはとても甘かった。
「嫌じゃなかったらおぶって保健室まで連れて行こうか?」
「そ、そんなっ、悪いです……っ」
彼女は更に頬を赤らめたまま、ふるふるとかぶりを振った。
潤んだ瞳は、身長差のせいで自ずと上目遣いになっており、それを目の当たりにした途端、依人の胸は騒ぎ出した。
(なんか放って置けないな……)
意図があるのかないのか定かではないが、彼女の仕草を見ていると、依人の中にある庇護欲がいたく刺激された。
「いいから背中に乗って」
依人はしゃがみこみ、おぶる体勢になった。
「し、失礼します……」
彼女はおずおずと依人に近寄ると、背中に乗ってぎゅっと肩に掴まった。
彼女が掴まっているのを確認すると、依人は立ち上がり、保健室まで歩き出した。
(軽い、)
内心彼女の軽さに目が丸くなった。
同年代の女子はダイエットに関心を持つ者が多いが、彼女の場合、これ以上痩せると身体が壊れてしまうのではないか。
そう思うほど依人は彼女に不安を覚えた。
保健室に辿り着くと、すぐさま彼女は養護教諭から手当てを受けた。
足はただの捻挫だった。
怪我の原因は、人とぶつかった時に転んでしまった拍子に足を捻らせてしまったようだった。
「名前書いてちょうだい」
養護教諭から保健室を利用した際に記帳する用紙を受け取り、彼女は小さな手でボールペンでさらさらと書いた。
“佐藤縁”
か弱い見た目に反して力強く達筆な字を目にした途端、依人はあることを思い出した。
“今年の新入生にレベルの高い女子が二人いる”
四月の入学式を終えた後、クラスの男子生徒がそう騒いでいた。
その内の一人が彼女……改め、目の前にいる縁だったのだ。
(これだけ可愛いと、男は放っておかないよな)
縁の整い過ぎた顔を見て、依人は内心納得したのだった。
一言で言うと可憐な美少女。
依人は思わず息を呑んだ。
「……」
振り向いたきり固まったまま無言を貫く彼女。
見る見る内に頬は赤く染まりだした。
「足、怪我しているよね?」
「……は、い」
依人がもう一度尋ねると、我に返った彼女は無言のまま躊躇いがちに小さく頷いた。
その声はとても小さいものだったが、鈴を転がしたようなソプラノはとても甘かった。
「嫌じゃなかったらおぶって保健室まで連れて行こうか?」
「そ、そんなっ、悪いです……っ」
彼女は更に頬を赤らめたまま、ふるふるとかぶりを振った。
潤んだ瞳は、身長差のせいで自ずと上目遣いになっており、それを目の当たりにした途端、依人の胸は騒ぎ出した。
(なんか放って置けないな……)
意図があるのかないのか定かではないが、彼女の仕草を見ていると、依人の中にある庇護欲がいたく刺激された。
「いいから背中に乗って」
依人はしゃがみこみ、おぶる体勢になった。
「し、失礼します……」
彼女はおずおずと依人に近寄ると、背中に乗ってぎゅっと肩に掴まった。
彼女が掴まっているのを確認すると、依人は立ち上がり、保健室まで歩き出した。
(軽い、)
内心彼女の軽さに目が丸くなった。
同年代の女子はダイエットに関心を持つ者が多いが、彼女の場合、これ以上痩せると身体が壊れてしまうのではないか。
そう思うほど依人は彼女に不安を覚えた。
保健室に辿り着くと、すぐさま彼女は養護教諭から手当てを受けた。
足はただの捻挫だった。
怪我の原因は、人とぶつかった時に転んでしまった拍子に足を捻らせてしまったようだった。
「名前書いてちょうだい」
養護教諭から保健室を利用した際に記帳する用紙を受け取り、彼女は小さな手でボールペンでさらさらと書いた。
“佐藤縁”
か弱い見た目に反して力強く達筆な字を目にした途端、依人はあることを思い出した。
“今年の新入生にレベルの高い女子が二人いる”
四月の入学式を終えた後、クラスの男子生徒がそう騒いでいた。
その内の一人が彼女……改め、目の前にいる縁だったのだ。
(これだけ可愛いと、男は放っておかないよな)
縁の整い過ぎた顔を見て、依人は内心納得したのだった。