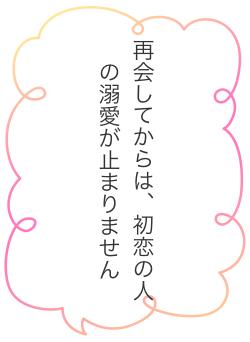耳元で囁かれると同時に、依人に力強く抱き締められていることに気付いた。
「やっと縁を抱き締められるんだ。もう離してあげられない。他の男に渡す気なんかないから」
「せんぱい……」
(あたし、先輩の彼女でいいんだ)
目が熱くなり、じわりと涙が溜まっていく。
その涙は、先ほどの不安から来るものではなく、喜びから来るものだった。
「縁、俺と一緒に住んでくれるかな?」
「はい……っ」
縁は涙を浮かべたまま笑顔で頷いた。
「ありがとう」
甘さが孕んだ瞳を向けられて、縁は魂が抜き取られたようにぼーっと夢見心地になっていた。
「ひゃっ」
ふと、左手に冷たい感覚が走り、縁は我に返った。
恐る恐る左手を見ると、薬指にキラリと輝くシンプルなシルバーの指輪がはめられていた。
「これは……」
「俺は二十歳になったばかりでまだ半人前だけど、将来縁と添い遂げたいって思ってる。だから――――」
次に聞こえた言葉に、縁は涙を抑えることが出来なかった。
“俺と結婚してくれませんか”
それは紛れもないプロポーズの言葉だった。
(あたし、果報者過ぎるよ……)
ついに縁は込み上げてくる涙を抑えられなくなり、小さな嗚咽を零し続ける。
「返事は?」
「こんなあたしでよければ……謹んでお受けします……っ」
依人は嬉し泣きをする縁を包み込むように優しく抱き締めた。
「一生かけて溺愛するから、覚悟してて?」
唇が重なり合う。
今までで一番幸せな気持ちになれる口付けだった。
「先輩、好き、大好きです」
「俺も誰よりも縁が好きだよ」
縁は、もっと溺れていたいと懇願するように依人の背中に腕を回した――――
あたしは、お姫様なんて柄じゃない。
だけど、どうかお願いです。
これからもずっと、あたしだけの王子様でいてください。
end.
「やっと縁を抱き締められるんだ。もう離してあげられない。他の男に渡す気なんかないから」
「せんぱい……」
(あたし、先輩の彼女でいいんだ)
目が熱くなり、じわりと涙が溜まっていく。
その涙は、先ほどの不安から来るものではなく、喜びから来るものだった。
「縁、俺と一緒に住んでくれるかな?」
「はい……っ」
縁は涙を浮かべたまま笑顔で頷いた。
「ありがとう」
甘さが孕んだ瞳を向けられて、縁は魂が抜き取られたようにぼーっと夢見心地になっていた。
「ひゃっ」
ふと、左手に冷たい感覚が走り、縁は我に返った。
恐る恐る左手を見ると、薬指にキラリと輝くシンプルなシルバーの指輪がはめられていた。
「これは……」
「俺は二十歳になったばかりでまだ半人前だけど、将来縁と添い遂げたいって思ってる。だから――――」
次に聞こえた言葉に、縁は涙を抑えることが出来なかった。
“俺と結婚してくれませんか”
それは紛れもないプロポーズの言葉だった。
(あたし、果報者過ぎるよ……)
ついに縁は込み上げてくる涙を抑えられなくなり、小さな嗚咽を零し続ける。
「返事は?」
「こんなあたしでよければ……謹んでお受けします……っ」
依人は嬉し泣きをする縁を包み込むように優しく抱き締めた。
「一生かけて溺愛するから、覚悟してて?」
唇が重なり合う。
今までで一番幸せな気持ちになれる口付けだった。
「先輩、好き、大好きです」
「俺も誰よりも縁が好きだよ」
縁は、もっと溺れていたいと懇願するように依人の背中に腕を回した――――
あたしは、お姫様なんて柄じゃない。
だけど、どうかお願いです。
これからもずっと、あたしだけの王子様でいてください。
end.