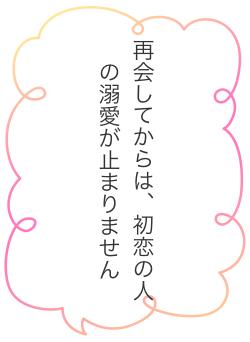縁が眠りに落ちてから一時間弱が経過した。
「ん……」
縁は目が覚めて、腕の中でもぞもぞと小さく動き出した。
「よく眠れた?」
縁は寝ぼけ眼のまましばらく依人の顔を凝視していたが、意識がはっきりとしてきたのか、次第に頬が赤らんでいき、勢いよく顔を俯かせた。
「ごめんなさいぃ……」
縁はただ恥ずかしさに耐え切れなくなっただけだろうが、俯く仕草が小動物のように愛らしく見えて、依人は思わず笑みを零した。
「縁が謝ることなんてないよ」
「だって、いっぱい泣いて、不満ぶつけた……」
「俺は一人で溜め込まれるよりはずっといいと思ってるよ」
「面倒臭いって思いませんか?」
「まさか」
依人はすかさず縁の腫れた瞼に口付けを落とした。
「先輩……」
縁の可憐な甘い声で呼ばれるだけで、背中にゾクゾクとした痺れが走る。
名前で呼ばれる日が来たら、理性が粉々に砕け散るのではないかと思うほどだ。
仮に他の女の人に言い寄られることが起きようが、何も感じないだろう。
出逢った頃から、手遅れなほど縁しか見えなくなっているのだから。
「遠距離は寂しいけど、一緒に頑張ろう」
「あたし達、乗り越えられますか?」
不安げに見つめる縁を、依人は力強く抱き締めた。
「乗り越える以外の選択肢はないから。縁が他の男に心変わりしても、攫うよ?」
「っ、先輩以外の人を好きになるなんて、有り得ませんっ!」
真っ直ぐな縁の言葉に、依人の鼓動は爆発しそうなほど暴れだした。
縁への想いは溺愛の域に達しているのに、後から尽きることなくどんどん溢れ出す。
「縁、」
依人は縁の頬を包み込んで、目線を合わせるように顔を上げさせる。
「縁が高校を卒業したら、必ず迎えにいくよ」
「っ!」
「だから、いい子で待ってくれるよね――はい以外は受け付けないよ」
縁が一字一句聞き逃さぬように、耳元で意図的に甘いトーンで囁いた。
強引だと思われても構わないと思った。
心も身体も、全ての手段を使ってでも自分のものにしたいと、依人は切実に願っていた。
縁の瞳は見張ったままだったが、やがて涙で潤んでとろけていく。
「はい……先輩を待ってます」
目を細めて破顔した縁。
その笑顔は、今までで一番綺麗ものだと感じた。
依人はそっと縁に優しく口付けを落としていった。
涙味のそれはしょっぱいはずなのに、何故か甘く感じた。
.
「ん……」
縁は目が覚めて、腕の中でもぞもぞと小さく動き出した。
「よく眠れた?」
縁は寝ぼけ眼のまましばらく依人の顔を凝視していたが、意識がはっきりとしてきたのか、次第に頬が赤らんでいき、勢いよく顔を俯かせた。
「ごめんなさいぃ……」
縁はただ恥ずかしさに耐え切れなくなっただけだろうが、俯く仕草が小動物のように愛らしく見えて、依人は思わず笑みを零した。
「縁が謝ることなんてないよ」
「だって、いっぱい泣いて、不満ぶつけた……」
「俺は一人で溜め込まれるよりはずっといいと思ってるよ」
「面倒臭いって思いませんか?」
「まさか」
依人はすかさず縁の腫れた瞼に口付けを落とした。
「先輩……」
縁の可憐な甘い声で呼ばれるだけで、背中にゾクゾクとした痺れが走る。
名前で呼ばれる日が来たら、理性が粉々に砕け散るのではないかと思うほどだ。
仮に他の女の人に言い寄られることが起きようが、何も感じないだろう。
出逢った頃から、手遅れなほど縁しか見えなくなっているのだから。
「遠距離は寂しいけど、一緒に頑張ろう」
「あたし達、乗り越えられますか?」
不安げに見つめる縁を、依人は力強く抱き締めた。
「乗り越える以外の選択肢はないから。縁が他の男に心変わりしても、攫うよ?」
「っ、先輩以外の人を好きになるなんて、有り得ませんっ!」
真っ直ぐな縁の言葉に、依人の鼓動は爆発しそうなほど暴れだした。
縁への想いは溺愛の域に達しているのに、後から尽きることなくどんどん溢れ出す。
「縁、」
依人は縁の頬を包み込んで、目線を合わせるように顔を上げさせる。
「縁が高校を卒業したら、必ず迎えにいくよ」
「っ!」
「だから、いい子で待ってくれるよね――はい以外は受け付けないよ」
縁が一字一句聞き逃さぬように、耳元で意図的に甘いトーンで囁いた。
強引だと思われても構わないと思った。
心も身体も、全ての手段を使ってでも自分のものにしたいと、依人は切実に願っていた。
縁の瞳は見張ったままだったが、やがて涙で潤んでとろけていく。
「はい……先輩を待ってます」
目を細めて破顔した縁。
その笑顔は、今までで一番綺麗ものだと感じた。
依人はそっと縁に優しく口付けを落としていった。
涙味のそれはしょっぱいはずなのに、何故か甘く感じた。
.