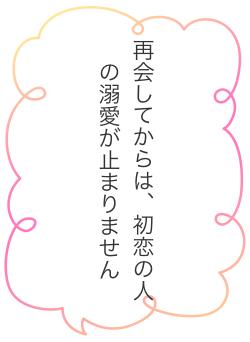>>依人視点
高梨弥生は、依人が中学三年の頃に付き合っていたかつての彼女だった。
同じ美化委員になったのがきっかけで話すようになり、弥生の穏やかな笑顔を隣で見ていたいと思うようになっていた。
いても経ってもいられなくなり、玉砕覚悟で告白をすると、弥生はいつもの穏やかな笑顔で「よろしくお願いします」と頷いてくれた。
クラスメイトから恋人同士になってからは、一緒にいることが増えるようになった。
ほんわかした温かい空気が好きだった。
しかし、二人の関係は卒業式の日に終止符を打った。
「――桜宮くん、私たち別れましょう」
学校から肩を並べて歩いている途中、弥生は前触れなく別れを告げた。
「え? 俺のこと、嫌になった?」
雑談するようにさらりと出てきた別れ話に、藪から棒に何を言い出すんだ? と依人は思わず眉を寄せてしまった。
「私、本当は桜宮くんに恋愛感情を持ってないの。本当に好きな人は小さい頃からいてね、私、一度は諦めようとあなたの告白を受け入れて利用したの……ごめんなさい」
弥生は親に怒られた小さな子どものように俯いた。
「分かったよ」
いきなりの別れを受け入れられるほど余裕がなかったが、無理に引き留めてもお互い幸せになれないと思った。
「私、また好きな人を振り向かせるように頑張るから、桜宮くんも幸せになってね……」
依人は無言で頷いた。
「俺、先に行くね」
二人きりが耐えられなくなって、依人は弥生の横を通り過ぎようとした。
その時、依人の耳に弥生の囁きが入った。
「いつか桜宮くんも出逢うよ。私なんか霞むくらいの素敵な運命の人にね」
弥生は優等生で、目鼻立ちのはっきりした顔立ちはしっかりしているように見えるが、実際はかなりの天然女子だ。
悪意はないのは理解しているが、思ったことを容赦なく言ってのけるところがある。
「そんな日が来るといいね」
依人は弥生の顔を見ずに返すと、そそくさと弥生を残して立ち去った。
もしかしたら明日出逢うかもしれない、逆に年老いて死ぬ間際に出逢うかもしれない。
どの道、依人はその運命の出逢いとやらに過度な期待を抱く気はなかった。
他人事のように大して気にも留めなかった。
頭の中にあるのは、弥生の穏やかで温かな笑顔だけ。
「っ、」
右目の目尻に涙を溜めていたのは、依人だけの秘密。
高梨弥生は、依人が中学三年の頃に付き合っていたかつての彼女だった。
同じ美化委員になったのがきっかけで話すようになり、弥生の穏やかな笑顔を隣で見ていたいと思うようになっていた。
いても経ってもいられなくなり、玉砕覚悟で告白をすると、弥生はいつもの穏やかな笑顔で「よろしくお願いします」と頷いてくれた。
クラスメイトから恋人同士になってからは、一緒にいることが増えるようになった。
ほんわかした温かい空気が好きだった。
しかし、二人の関係は卒業式の日に終止符を打った。
「――桜宮くん、私たち別れましょう」
学校から肩を並べて歩いている途中、弥生は前触れなく別れを告げた。
「え? 俺のこと、嫌になった?」
雑談するようにさらりと出てきた別れ話に、藪から棒に何を言い出すんだ? と依人は思わず眉を寄せてしまった。
「私、本当は桜宮くんに恋愛感情を持ってないの。本当に好きな人は小さい頃からいてね、私、一度は諦めようとあなたの告白を受け入れて利用したの……ごめんなさい」
弥生は親に怒られた小さな子どものように俯いた。
「分かったよ」
いきなりの別れを受け入れられるほど余裕がなかったが、無理に引き留めてもお互い幸せになれないと思った。
「私、また好きな人を振り向かせるように頑張るから、桜宮くんも幸せになってね……」
依人は無言で頷いた。
「俺、先に行くね」
二人きりが耐えられなくなって、依人は弥生の横を通り過ぎようとした。
その時、依人の耳に弥生の囁きが入った。
「いつか桜宮くんも出逢うよ。私なんか霞むくらいの素敵な運命の人にね」
弥生は優等生で、目鼻立ちのはっきりした顔立ちはしっかりしているように見えるが、実際はかなりの天然女子だ。
悪意はないのは理解しているが、思ったことを容赦なく言ってのけるところがある。
「そんな日が来るといいね」
依人は弥生の顔を見ずに返すと、そそくさと弥生を残して立ち去った。
もしかしたら明日出逢うかもしれない、逆に年老いて死ぬ間際に出逢うかもしれない。
どの道、依人はその運命の出逢いとやらに過度な期待を抱く気はなかった。
他人事のように大して気にも留めなかった。
頭の中にあるのは、弥生の穏やかで温かな笑顔だけ。
「っ、」
右目の目尻に涙を溜めていたのは、依人だけの秘密。