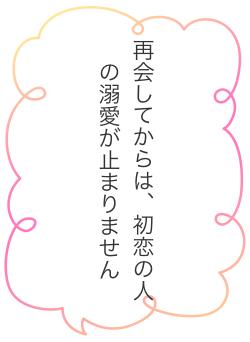「うっ、ひっく……怖いよ……っ」
ここ数日、縁は不安しかなかった。
スマートフォンで遠距離恋愛について検索をしたら、破局したケースばかりがごろごろと出てきた。
どう足掻いても、距離が離れてしまうと寄り添っていた心も離れてしまうのか。
依人の中から自分がいなくなってしまう日が来てしまうのか。
(先輩がほかの人を好きになるなんて、想像するだけで胸が痛い)
胸が張り裂けそうになり、夜は中々眠れなかった。
縁は鈴子に抱き着いて、ただただ静かに嗚咽を零し続けた。
キッチンに甘い匂いが漂いだした頃、縁の涙腺は落ち着きを取り戻した。
「落ち着いた?」
鈴子は優しく微笑みながら、ハンカチで目尻に溜まった涙を拭い取る。
「うん……ありがとう」
縁は泣き腫らした目を恥ずかしげに伏せてお礼を言った。
「こんなに腫らして……今まで独りで泣いていたんでしょ」
「うん……最初お母さんを無視しちゃったから、これ以上泣いて困らせちゃいけないって無理して笑ってたの」
「あたしがいる時は無理しなくていいわよ。受け止めてあげるから」
「ふふっ、鈴子ったら男前」
「嬉しくない褒め言葉」
鈴子は口ではそう返していたが、笑みが零れていた。
(鈴子、あたしの友達でいてくれてありがとう。本当に感謝してもし足りないよ)
「ありがとう、鈴子」
縁は鈴子に心から強く感謝した。
オーブンから焼き上がりを知らせるアラームが鳴り出す。
ミトンをはめて、オーブンを開けると、甘いチョコレートの香りが鼻をくすぐった。
「どう?」
オーブンの中を覗き込む鈴子に、縁は親指をぐっと立てた。
竹串で生焼けがないかを確認した後、二人は試食と称したティータイムを始めた。
「美味しい」
「これなら渡せるわね」
口に入れると、程よい甘さと苦さと、中に入っているくるみの香ばしさが広がった。
出来栄えは自画自賛してしまうほど成功した。
試食を終えると、粗熱が取れたブラウニーをラッピングをし、チョコレート作りは終了した。
「頑張ってね」
「鈴子もねっ」
二人はお互い健闘を祈りながら、バイバイと別れた。
ここ数日、縁は不安しかなかった。
スマートフォンで遠距離恋愛について検索をしたら、破局したケースばかりがごろごろと出てきた。
どう足掻いても、距離が離れてしまうと寄り添っていた心も離れてしまうのか。
依人の中から自分がいなくなってしまう日が来てしまうのか。
(先輩がほかの人を好きになるなんて、想像するだけで胸が痛い)
胸が張り裂けそうになり、夜は中々眠れなかった。
縁は鈴子に抱き着いて、ただただ静かに嗚咽を零し続けた。
キッチンに甘い匂いが漂いだした頃、縁の涙腺は落ち着きを取り戻した。
「落ち着いた?」
鈴子は優しく微笑みながら、ハンカチで目尻に溜まった涙を拭い取る。
「うん……ありがとう」
縁は泣き腫らした目を恥ずかしげに伏せてお礼を言った。
「こんなに腫らして……今まで独りで泣いていたんでしょ」
「うん……最初お母さんを無視しちゃったから、これ以上泣いて困らせちゃいけないって無理して笑ってたの」
「あたしがいる時は無理しなくていいわよ。受け止めてあげるから」
「ふふっ、鈴子ったら男前」
「嬉しくない褒め言葉」
鈴子は口ではそう返していたが、笑みが零れていた。
(鈴子、あたしの友達でいてくれてありがとう。本当に感謝してもし足りないよ)
「ありがとう、鈴子」
縁は鈴子に心から強く感謝した。
オーブンから焼き上がりを知らせるアラームが鳴り出す。
ミトンをはめて、オーブンを開けると、甘いチョコレートの香りが鼻をくすぐった。
「どう?」
オーブンの中を覗き込む鈴子に、縁は親指をぐっと立てた。
竹串で生焼けがないかを確認した後、二人は試食と称したティータイムを始めた。
「美味しい」
「これなら渡せるわね」
口に入れると、程よい甘さと苦さと、中に入っているくるみの香ばしさが広がった。
出来栄えは自画自賛してしまうほど成功した。
試食を終えると、粗熱が取れたブラウニーをラッピングをし、チョコレート作りは終了した。
「頑張ってね」
「鈴子もねっ」
二人はお互い健闘を祈りながら、バイバイと別れた。