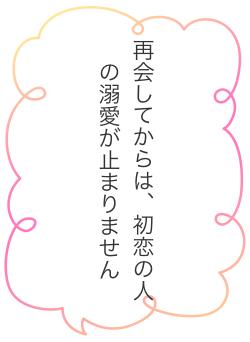母からの転校の話を聞かされて、縁は数日間母と口を聞かなくなったが、少しだけ冷静さを取り戻すと、母に無視したことを謝り、話を受け止めた。
父が亡くなってからずっと自分の養う為に男の人にも負けないくらい働いてくれた母。
意地悪をしたくて転校の話をした訳がないと言うのに、優しい母を無視をするなんてまだまだ子どもだと反省した。
この生まれ育った家は春には空き家になるのかと思われたが、医学部に通う母方の従兄に貸すのだと母が教えてくれた。
「縁、本当にごめんね? 依人くんや鈴子ちゃんと離れ離れにさせるなんて酷だと思ってる」
荷物をまとめていると、母は眉を下げて申し訳なさそうに縁に謝った。
「気にしないで。あたしはもう大丈夫だから。お母さんについていって支えるよ。それに、北海道は初めてだから今は新しい生活が楽しみなの」
本当は今でもこの街に残りたいと切実に願っているが、縁はこれ以上母を困らせたくなくて本音を押し殺し、笑顔を貼り付けた。
「お仕事ない日は一緒に美味しいものを食べに行こうねっ」
「……そうね」
母は縁の髪を撫でながら笑顔で頷いた。
(先輩、遠距離になるって知ったらなんて言うかな……)
縁の心に植え付けられた不安の種は、芽吹いて日々大きく育っていった――――
時は流れて、バレンタインデーの前日になった。
今年のバレンタインデーは日曜日と重なり、縁はその日依人とデートをすることとなった。
前日のこの日、学校が終わると、自宅のキッチンで鈴子とお菓子作りに勤しんでいた。
「縁、先輩には話をしたの?」
オーブンでブラウニーを焼いている時、鈴子は神妙な顔で縁に尋ねた。
鈴子には転校の話を聞かされた翌日に打ち明けた。
正確には腫れぼったい瞼に目敏く気付き問い質されたのだが。
依人にはまだ打ち明けられずにいた。
不幸中の幸いか、依人は自動車の運転免許を取りに自動車学校に通い始めたので、顔を合わせることはなく、まだ縁の様子に気付いていない。
「明日話すよ。いつまでも隠せないから」
縁はにこりと微笑んだが、鈴子はその笑顔が気に食わなかったのか頬を抓った。
手加減なしの痛さに思わず眉を寄せてしまう。
「いひゃいっ」
「あたしの前で無理して笑わなくていいわよ。本当は泣きたいんでしょ?」
「鈴子……」
縁から次第に笑顔は消え失せ、水道の蛇口を捻ったように大きな瞳かはボロボロと涙が溢れ出した。
父が亡くなってからずっと自分の養う為に男の人にも負けないくらい働いてくれた母。
意地悪をしたくて転校の話をした訳がないと言うのに、優しい母を無視をするなんてまだまだ子どもだと反省した。
この生まれ育った家は春には空き家になるのかと思われたが、医学部に通う母方の従兄に貸すのだと母が教えてくれた。
「縁、本当にごめんね? 依人くんや鈴子ちゃんと離れ離れにさせるなんて酷だと思ってる」
荷物をまとめていると、母は眉を下げて申し訳なさそうに縁に謝った。
「気にしないで。あたしはもう大丈夫だから。お母さんについていって支えるよ。それに、北海道は初めてだから今は新しい生活が楽しみなの」
本当は今でもこの街に残りたいと切実に願っているが、縁はこれ以上母を困らせたくなくて本音を押し殺し、笑顔を貼り付けた。
「お仕事ない日は一緒に美味しいものを食べに行こうねっ」
「……そうね」
母は縁の髪を撫でながら笑顔で頷いた。
(先輩、遠距離になるって知ったらなんて言うかな……)
縁の心に植え付けられた不安の種は、芽吹いて日々大きく育っていった――――
時は流れて、バレンタインデーの前日になった。
今年のバレンタインデーは日曜日と重なり、縁はその日依人とデートをすることとなった。
前日のこの日、学校が終わると、自宅のキッチンで鈴子とお菓子作りに勤しんでいた。
「縁、先輩には話をしたの?」
オーブンでブラウニーを焼いている時、鈴子は神妙な顔で縁に尋ねた。
鈴子には転校の話を聞かされた翌日に打ち明けた。
正確には腫れぼったい瞼に目敏く気付き問い質されたのだが。
依人にはまだ打ち明けられずにいた。
不幸中の幸いか、依人は自動車の運転免許を取りに自動車学校に通い始めたので、顔を合わせることはなく、まだ縁の様子に気付いていない。
「明日話すよ。いつまでも隠せないから」
縁はにこりと微笑んだが、鈴子はその笑顔が気に食わなかったのか頬を抓った。
手加減なしの痛さに思わず眉を寄せてしまう。
「いひゃいっ」
「あたしの前で無理して笑わなくていいわよ。本当は泣きたいんでしょ?」
「鈴子……」
縁から次第に笑顔は消え失せ、水道の蛇口を捻ったように大きな瞳かはボロボロと涙が溢れ出した。