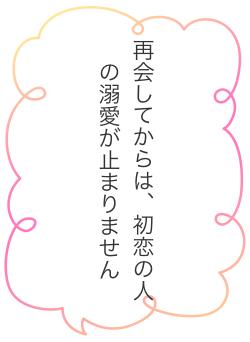井坂事件(鈴子による命名)をどうにか乗り越え、縁と依人はこれまで通り仲睦まじくお付き合いを続けていた。
月日が流れ、残暑の厳しい九月からコートが手放せなくなった十二月に差し掛かった。
「お母さん」
「どうしたの? 急に改まって」
十二月中旬のある日の晩、仕事から帰ってきた母と夕飯を摂っていると、縁は緊張した面持ちで切り出した。
「二十四日なんだけど、少し遠出するから帰るのが遅くなります……」
この時の縁は、母親に対して敬語になってしまうほど緊張していた。
何故なら二十四日、所謂クリスマスイブ、依人とイルミネーションを見に行くことに決まったからだ。
夜のデートは夏の祭り以来になる。
祭りの時は丁度母は出張中だったので言っていないが、イブ当日は母の仕事が休みで家にいる予定のであらかじめ伝えることにした。
全ては言わなかったが、縁の様子を見て何かを察したように母はニヤリと笑みを浮かべた。
「……いつ彼氏が出来たのかなぁ?」
「っ、し、七月」
(茶化されるのは避けて通れないな)
縁は気恥しさを紛らわすように、鯵の塩焼きの身を器用に解していく。
母は微笑ましそうに縁を見つめていた。
「ふふ。奥手で本ばっかり読んでた縁が彼氏かぁ。いいなぁ、青春ね」
「もう、やめてよぉ」
縁は眉を寄せて拗ねた表情をさせるが、母は相変わらず笑顔だ。
「お母さん反対しないから、楽しんできなさい」
「あ、ありがとう……」
何はともあれ、夜の外出のお許しが出たので、縁はほっと肩を撫で下ろした。
「あぁ!」
夕飯を食べ終えて、食器を洗っていると、リビングでお茶を飲んで寛いでいる母の大きな声が耳に入った。
「お母さん、どうしたの?」
泡立つスポンジを手にリビングの方へ振り返ると、
「いいものがあるの。ちょっと取ってくるね〜」
母は慌ただしくスリッパをパタパタと鳴らしながら、階段を勢いよく駆け上がって行った。
(なんだろう……)
縁は疑問に思いながら残った食器を洗う。
全てを洗い終えた後、同じタイミングで母は二階から戻って来て、縁の元へ近寄った。
「これ、縁にあげる。忘年会のくじ引きで当てたの」
ふふ、と娘から見ても可愛らしい笑みを見せながら、母は縁の目の前で差し出した。
それはとある有名なホテルの宿泊券だった。
月日が流れ、残暑の厳しい九月からコートが手放せなくなった十二月に差し掛かった。
「お母さん」
「どうしたの? 急に改まって」
十二月中旬のある日の晩、仕事から帰ってきた母と夕飯を摂っていると、縁は緊張した面持ちで切り出した。
「二十四日なんだけど、少し遠出するから帰るのが遅くなります……」
この時の縁は、母親に対して敬語になってしまうほど緊張していた。
何故なら二十四日、所謂クリスマスイブ、依人とイルミネーションを見に行くことに決まったからだ。
夜のデートは夏の祭り以来になる。
祭りの時は丁度母は出張中だったので言っていないが、イブ当日は母の仕事が休みで家にいる予定のであらかじめ伝えることにした。
全ては言わなかったが、縁の様子を見て何かを察したように母はニヤリと笑みを浮かべた。
「……いつ彼氏が出来たのかなぁ?」
「っ、し、七月」
(茶化されるのは避けて通れないな)
縁は気恥しさを紛らわすように、鯵の塩焼きの身を器用に解していく。
母は微笑ましそうに縁を見つめていた。
「ふふ。奥手で本ばっかり読んでた縁が彼氏かぁ。いいなぁ、青春ね」
「もう、やめてよぉ」
縁は眉を寄せて拗ねた表情をさせるが、母は相変わらず笑顔だ。
「お母さん反対しないから、楽しんできなさい」
「あ、ありがとう……」
何はともあれ、夜の外出のお許しが出たので、縁はほっと肩を撫で下ろした。
「あぁ!」
夕飯を食べ終えて、食器を洗っていると、リビングでお茶を飲んで寛いでいる母の大きな声が耳に入った。
「お母さん、どうしたの?」
泡立つスポンジを手にリビングの方へ振り返ると、
「いいものがあるの。ちょっと取ってくるね〜」
母は慌ただしくスリッパをパタパタと鳴らしながら、階段を勢いよく駆け上がって行った。
(なんだろう……)
縁は疑問に思いながら残った食器を洗う。
全てを洗い終えた後、同じタイミングで母は二階から戻って来て、縁の元へ近寄った。
「これ、縁にあげる。忘年会のくじ引きで当てたの」
ふふ、と娘から見ても可愛らしい笑みを見せながら、母は縁の目の前で差し出した。
それはとある有名なホテルの宿泊券だった。