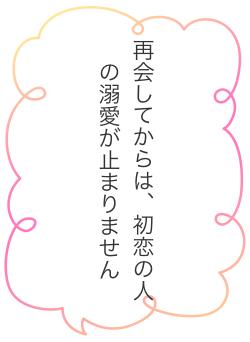カフェを後にして、いつものように手を繋いで縁を自宅まで送り届ける。
縁は異性からどう思われているか無頓着だ。
無防備で危なっかしいので、一人で帰す真似は依人にはとても出来なかった。
祭りの日……縁から着いたと言う連絡が待ち合わせ時間の三十分以上前に来た時は肝が冷えた。
この時依人は、一人にさせてたまるか、と速攻準備を終えて全速力で向かったことは縁は知る由もない。
「いつも、ありがとうございます」
佐藤家に到着すると、縁は丁寧に頭を下げて依人にお礼を言う。
「彼氏として当然の務めだよ」
名残惜しさを感じながら繋いだ手をゆっくり解いていく。
明日も学校があるので会えるのだが、毎日顔を合わせても足りないと思ってしまう。
(前までは重いタイプじゃなかったのにな)
束縛する気は毛頭ないが、独占欲が日々大きくなっている自覚が依人にはあった。
「先輩……」
突然、縁は解きかけた手をぎゅっと握り締めた。
「ん、どうしたの――――」
その時、目の前で起きた状況に依人は目を見張った。
可愛らしいリップノイズが耳に届いた。
縁の小さな唇が依人の手の甲に触れたのだ。
「ゆかり……」
奥手な縁からは想像出来ない行動に、依人は動揺を隠せず呆然と縁を見つめるしか出来ない。
「本屋さんで、女の先輩が、先輩の手をぎゅってしたから、しょ、消毒です……っ」
二年の女子生徒に連絡先のメモを握らされた場面を見ていたようだ。
縁は真っ赤な顔をさせて吃りながら言うと、恥ずかしさに耐え切れなくなったのか、「さようならっ!」と脱兎のごとく駆け出して家の中に入っていった。
縁がいなくなって、依人は思わず手で口元を押さえた。
「今の反則だろ……」
初めて見る縁の嫉妬に、不安にさせて悪いという気持ちと、可愛いという気持ちがせめぎ合っていた。
(本当、勘弁して……好き過ぎておかしくなりそう)
依人は自分の髪をぐしゃりと掴むと盛大に嘆息した。
縁は異性からどう思われているか無頓着だ。
無防備で危なっかしいので、一人で帰す真似は依人にはとても出来なかった。
祭りの日……縁から着いたと言う連絡が待ち合わせ時間の三十分以上前に来た時は肝が冷えた。
この時依人は、一人にさせてたまるか、と速攻準備を終えて全速力で向かったことは縁は知る由もない。
「いつも、ありがとうございます」
佐藤家に到着すると、縁は丁寧に頭を下げて依人にお礼を言う。
「彼氏として当然の務めだよ」
名残惜しさを感じながら繋いだ手をゆっくり解いていく。
明日も学校があるので会えるのだが、毎日顔を合わせても足りないと思ってしまう。
(前までは重いタイプじゃなかったのにな)
束縛する気は毛頭ないが、独占欲が日々大きくなっている自覚が依人にはあった。
「先輩……」
突然、縁は解きかけた手をぎゅっと握り締めた。
「ん、どうしたの――――」
その時、目の前で起きた状況に依人は目を見張った。
可愛らしいリップノイズが耳に届いた。
縁の小さな唇が依人の手の甲に触れたのだ。
「ゆかり……」
奥手な縁からは想像出来ない行動に、依人は動揺を隠せず呆然と縁を見つめるしか出来ない。
「本屋さんで、女の先輩が、先輩の手をぎゅってしたから、しょ、消毒です……っ」
二年の女子生徒に連絡先のメモを握らされた場面を見ていたようだ。
縁は真っ赤な顔をさせて吃りながら言うと、恥ずかしさに耐え切れなくなったのか、「さようならっ!」と脱兎のごとく駆け出して家の中に入っていった。
縁がいなくなって、依人は思わず手で口元を押さえた。
「今の反則だろ……」
初めて見る縁の嫉妬に、不安にさせて悪いという気持ちと、可愛いという気持ちがせめぎ合っていた。
(本当、勘弁して……好き過ぎておかしくなりそう)
依人は自分の髪をぐしゃりと掴むと盛大に嘆息した。