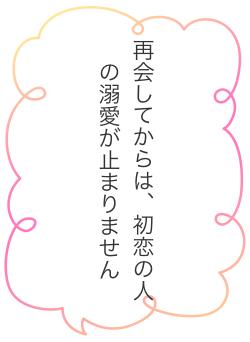(わ、格好いい……!)
真剣な眼差しをした依人の顔は凛々しくて、それがまた縁をドキドキさせた。
「どうぞ」
見事に狙いを決めた図書券を依人から受け取る。
「ありがとうございますっ」
縁は零れ落ちそうな大きな瞳を細めて、満面の笑みを浮かべた。
嬉しくなるのは図書券が手に入っただけじゃない。
依人が自分の為に取ってくれたから。
「それで好きな本買ってね?」
「それなら先輩の好きな本買ってみてもいいですか?」
縁は何気なく思ったことを尋ねると、依人は突然手のひらで口元を押さえた。
「……は……だって」
何か独りごちたようだが、縁にはよく聞こえなかった。
「真似は嫌ですよね。変なこと聞いてごめんなさいっ」
(たまに思ったことを何も考えずに言っちゃうのは、あたしの悪い癖だぁ!)
依人が気に障ったと思うと少し自己嫌悪になり、しゅんと顔を俯かせると。
「それはないからっ」
依人は慌てて否定をした。
「そうなんですか?」
「今のは変に照れちゃっただけ。嬉しかったんだよ。縁がどんな形でも俺に興味を持ってくれたんだって」
その言葉に縁は安堵した。
依人の態度は嫌悪から来たものでないと分かったから。
「良かったです……」
(先輩に嫌われなくて……そうなったらあたしは立ち直れないよ)
潤んだ瞳のまま微笑んだ。
一通り縁日を楽しんだ後、二人は長い石段を休みながら登っていく。
この縁日は花火大会も行われており、長い石段の先にある境内は花火がよく見える絶好のスポットだった。
「痛っ……」
しかし、縁は鼻緒で擦れたせいで足の指を痛めてしまった。
「大丈夫?」
「はい。ちょっと鼻緒で擦れて……後で追い掛けるので先に行ってください」
頂上の境内まで石段はあと十数段だが、今の縁にはとてつもなく長く見える。
「縁を置いていく真似は出来ないよ」
「でも、もうすぐ始まりますよ。先輩だけでも先に楽しんでください」
「それなら、」
依人は縁の目線に合わせて膝を折ると、腕を縁の膝裏に通して抱き上げた。
「きゃっ」
いきなりの浮遊感に、思わず小さな悲鳴を上げる。
「重いですよ……っ」
縁は慌てて暗に降ろしてくれと懇願するが、依人は降ろすことなく縁をお姫様抱っこしたまま石段を登っていく。
真剣な眼差しをした依人の顔は凛々しくて、それがまた縁をドキドキさせた。
「どうぞ」
見事に狙いを決めた図書券を依人から受け取る。
「ありがとうございますっ」
縁は零れ落ちそうな大きな瞳を細めて、満面の笑みを浮かべた。
嬉しくなるのは図書券が手に入っただけじゃない。
依人が自分の為に取ってくれたから。
「それで好きな本買ってね?」
「それなら先輩の好きな本買ってみてもいいですか?」
縁は何気なく思ったことを尋ねると、依人は突然手のひらで口元を押さえた。
「……は……だって」
何か独りごちたようだが、縁にはよく聞こえなかった。
「真似は嫌ですよね。変なこと聞いてごめんなさいっ」
(たまに思ったことを何も考えずに言っちゃうのは、あたしの悪い癖だぁ!)
依人が気に障ったと思うと少し自己嫌悪になり、しゅんと顔を俯かせると。
「それはないからっ」
依人は慌てて否定をした。
「そうなんですか?」
「今のは変に照れちゃっただけ。嬉しかったんだよ。縁がどんな形でも俺に興味を持ってくれたんだって」
その言葉に縁は安堵した。
依人の態度は嫌悪から来たものでないと分かったから。
「良かったです……」
(先輩に嫌われなくて……そうなったらあたしは立ち直れないよ)
潤んだ瞳のまま微笑んだ。
一通り縁日を楽しんだ後、二人は長い石段を休みながら登っていく。
この縁日は花火大会も行われており、長い石段の先にある境内は花火がよく見える絶好のスポットだった。
「痛っ……」
しかし、縁は鼻緒で擦れたせいで足の指を痛めてしまった。
「大丈夫?」
「はい。ちょっと鼻緒で擦れて……後で追い掛けるので先に行ってください」
頂上の境内まで石段はあと十数段だが、今の縁にはとてつもなく長く見える。
「縁を置いていく真似は出来ないよ」
「でも、もうすぐ始まりますよ。先輩だけでも先に楽しんでください」
「それなら、」
依人は縁の目線に合わせて膝を折ると、腕を縁の膝裏に通して抱き上げた。
「きゃっ」
いきなりの浮遊感に、思わず小さな悲鳴を上げる。
「重いですよ……っ」
縁は慌てて暗に降ろしてくれと懇願するが、依人は降ろすことなく縁をお姫様抱っこしたまま石段を登っていく。