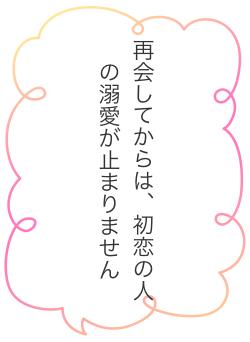「縁」
依人の甘い声が耳に入ると同時に手に温もりが伝わった。
「っ……」
手を握られて、鼓動は更に激しくなっていく。
「絶対俺から離れないで」
「はい。迷子にならないようにしますっ」
大きく頷くと、依人は眉を下げて困った風に笑った。
「俺の意図が分かってないね」
「意図……?」
(迷子になられると困るからじゃないの?)
依人の言う意図が縁には分からず、首を傾げた。
「自分が可愛いこと自覚してる?」
「ま、まさか!」
(自覚してるなんてナルシストみたいだよっ)
縁は否定するようにかぶりを大きく振った。
「やっぱり……」
依人は縁の反応見をて肩を竦めた。
そして、小柄な縁の目線に合わせるように膝を折り、肩に手を乗せると、小さな子に言い聞かせるように諭した。
「縁は可愛いよ。縁を食べようと狙っている輩がうようよいるくらいにね」
「っ!」
依人の整った顔が近い。
心臓が壊れそうになり、顔を背けようとしたが、肩に置いた手は縁の頬を包み、そらせなくなった。
「縁がそいつらのせいで危険な目に遭うのは嫌なんだよ。何より――――俺以外の男に指一本も触れさせたくない」
依人の目は真剣な眼差しに変わり、いつもより低い声で縁の耳元で囁いた。
縁の顔は、浴衣に描かれた椿の花びらと同じくらい真っ赤だった。
(そんな事言われたら勘違いしそうになるよ……っ。先輩に愛されているんだって)
「だから、今日はずっと俺の傍にいること。分かった?」
「はい……っ」
縁は自分の浴衣の袖をぎゅっと握り締めながら、こくりと頷いた。
依人の甘い声が耳に入ると同時に手に温もりが伝わった。
「っ……」
手を握られて、鼓動は更に激しくなっていく。
「絶対俺から離れないで」
「はい。迷子にならないようにしますっ」
大きく頷くと、依人は眉を下げて困った風に笑った。
「俺の意図が分かってないね」
「意図……?」
(迷子になられると困るからじゃないの?)
依人の言う意図が縁には分からず、首を傾げた。
「自分が可愛いこと自覚してる?」
「ま、まさか!」
(自覚してるなんてナルシストみたいだよっ)
縁は否定するようにかぶりを大きく振った。
「やっぱり……」
依人は縁の反応見をて肩を竦めた。
そして、小柄な縁の目線に合わせるように膝を折り、肩に手を乗せると、小さな子に言い聞かせるように諭した。
「縁は可愛いよ。縁を食べようと狙っている輩がうようよいるくらいにね」
「っ!」
依人の整った顔が近い。
心臓が壊れそうになり、顔を背けようとしたが、肩に置いた手は縁の頬を包み、そらせなくなった。
「縁がそいつらのせいで危険な目に遭うのは嫌なんだよ。何より――――俺以外の男に指一本も触れさせたくない」
依人の目は真剣な眼差しに変わり、いつもより低い声で縁の耳元で囁いた。
縁の顔は、浴衣に描かれた椿の花びらと同じくらい真っ赤だった。
(そんな事言われたら勘違いしそうになるよ……っ。先輩に愛されているんだって)
「だから、今日はずっと俺の傍にいること。分かった?」
「はい……っ」
縁は自分の浴衣の袖をぎゅっと握り締めながら、こくりと頷いた。