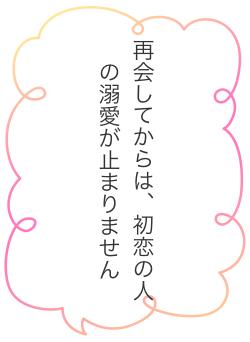「そうだね。北川さんの言う通り、縁は本当に頑張っていたから用意してあげなきゃね」
「だって、よかったね」
「ひゃっ!」
鈴子は縁にやんわりとひじで小突くと、わしゃわしゃと犬や猫のように頭を撫で回した。
「縁、ご褒美なにがいい?」
「そんな、気持ちだけで充分ですよ? お祭りに連れて行ってくれるだけでも立派なご褒美ですからっ」
鈴子に撫で回されて乱れた髪をそのままに、縁は照れ気味に呟いた。
「祭り以外はないの? なんでも言ってみて」
依人はくすっと笑いながら、手櫛で縁の髪を直す。
「えっと」
(いきなり言われても分からないよ……)
何も思い付かず、戸惑ってしまう。
「まあ、考えといて」
「は、はい」
「また放課後」
依人はまた縁の髪を撫でると、立ち去って行った。
「何でも言ってって、愛されているわねー」
もう少しで午後の授業が始まるので、移動していると鈴子はにこにこしながら縁を茶化す。
「そんな、好きなのはあたしだけだよ……」
縁は鈴子の言葉を否定するように小さくかぶりを振った。
(自分で言ってて悲しい……)
「何を根拠にそう思うの?」
鈴子は縁の発言を信じられないと言いたげに訝しむ。
「だって、先輩はあたしを送り迎えする時、一人で歩かせたくないって……それってあたしのこと子どもにしか見てないって意味でしょ? きっと、あたしは暇つぶしなの」
「それはね……」
「それにっ、まだ、先輩はしてこない……き、キス」
蚊の鳴くような声で鈴子に耳打ちすると、
「それならご褒美は――――」
鈴子は誰にも聞こえないように縁に耳打ちした。
それを聞いて縁の頬は瞬時に赤くなる。
「そんな、あたしから言うなんて……っ」
「大丈夫。縁がお願いしたら、絶対先輩喜んでくれるって」
鈴子は縁に親指を立てて、自信満々に言い切った。
「だって、よかったね」
「ひゃっ!」
鈴子は縁にやんわりとひじで小突くと、わしゃわしゃと犬や猫のように頭を撫で回した。
「縁、ご褒美なにがいい?」
「そんな、気持ちだけで充分ですよ? お祭りに連れて行ってくれるだけでも立派なご褒美ですからっ」
鈴子に撫で回されて乱れた髪をそのままに、縁は照れ気味に呟いた。
「祭り以外はないの? なんでも言ってみて」
依人はくすっと笑いながら、手櫛で縁の髪を直す。
「えっと」
(いきなり言われても分からないよ……)
何も思い付かず、戸惑ってしまう。
「まあ、考えといて」
「は、はい」
「また放課後」
依人はまた縁の髪を撫でると、立ち去って行った。
「何でも言ってって、愛されているわねー」
もう少しで午後の授業が始まるので、移動していると鈴子はにこにこしながら縁を茶化す。
「そんな、好きなのはあたしだけだよ……」
縁は鈴子の言葉を否定するように小さくかぶりを振った。
(自分で言ってて悲しい……)
「何を根拠にそう思うの?」
鈴子は縁の発言を信じられないと言いたげに訝しむ。
「だって、先輩はあたしを送り迎えする時、一人で歩かせたくないって……それってあたしのこと子どもにしか見てないって意味でしょ? きっと、あたしは暇つぶしなの」
「それはね……」
「それにっ、まだ、先輩はしてこない……き、キス」
蚊の鳴くような声で鈴子に耳打ちすると、
「それならご褒美は――――」
鈴子は誰にも聞こえないように縁に耳打ちした。
それを聞いて縁の頬は瞬時に赤くなる。
「そんな、あたしから言うなんて……っ」
「大丈夫。縁がお願いしたら、絶対先輩喜んでくれるって」
鈴子は縁に親指を立てて、自信満々に言い切った。