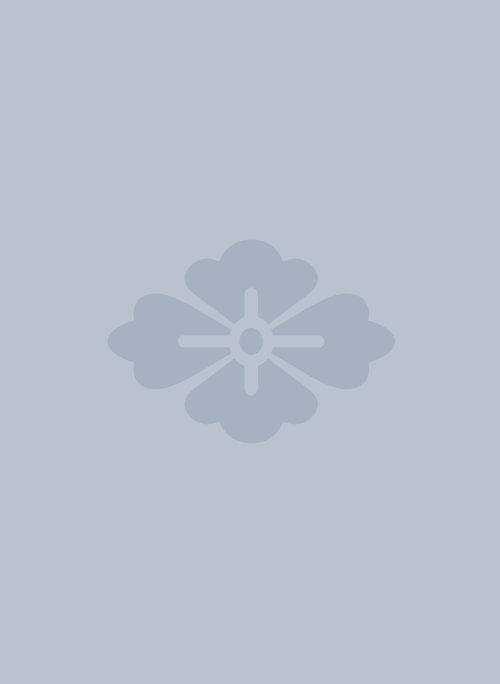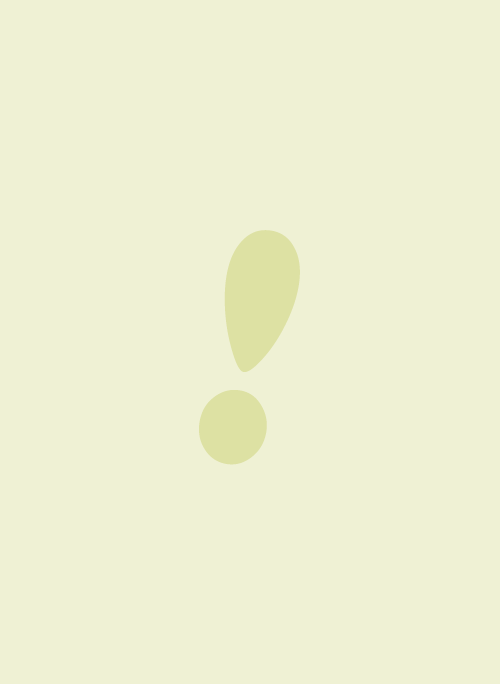しかし、惣次郎はそんなに柔ではなかった。
「侮辱など、してはいませぬ。私は剣術がどれ程今のこの国に必要なのか、分かっているつもりです。もしも、許されるものなら、私も剣を握りとぉ存じます。」
私は顔を綻ばせた。
「よく言ったぞ、惣次郎。よし、貴公に天然理心流を授けようじゃないか。」
「はい。勝太先生。」
惣次郎、あいつの目の輝きはこの日から変わらず澄んでいた。
「侮辱など、してはいませぬ。私は剣術がどれ程今のこの国に必要なのか、分かっているつもりです。もしも、許されるものなら、私も剣を握りとぉ存じます。」
私は顔を綻ばせた。
「よく言ったぞ、惣次郎。よし、貴公に天然理心流を授けようじゃないか。」
「はい。勝太先生。」
惣次郎、あいつの目の輝きはこの日から変わらず澄んでいた。