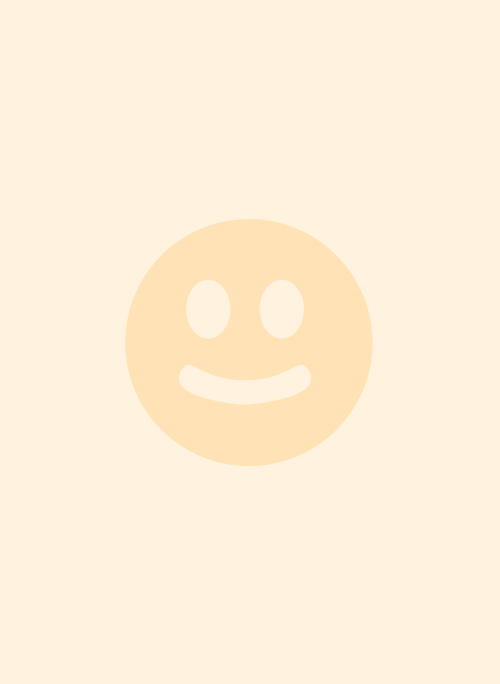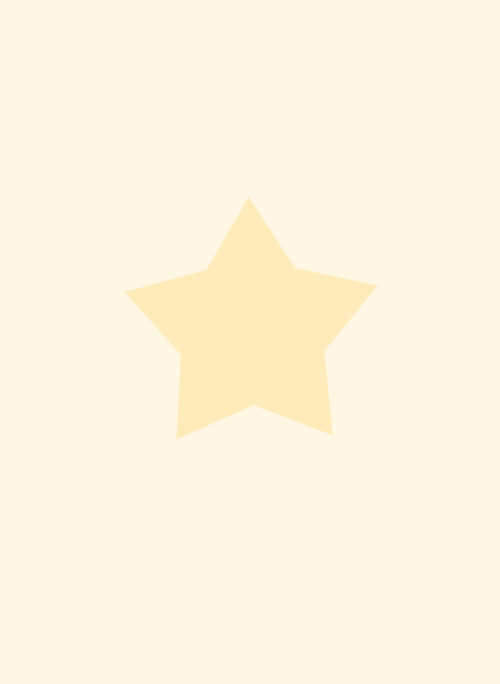「ーーーーー・・・・・・『痛い』って、言ったとして、どうなるの」
かすれた声。
ハロスを見上げる目はどこか無表情で、しかしその目はうっすらと濡れていた。
「そんなことを言って騒ぎにでもなったら私の家の名誉に傷がつくかもしれないでしょう。そしたら大変よ。損をする人しかいないわ。誰も得をしない。
それなら黙ってる方が無難だわ。私が口を開いたって喜ぶ人なんていないもの」
機械的に流れる言葉は、まるでロボットが入力された文章を読み上げるかのように淡々としていて、感情の起伏を感じなかった。
虚ろな瞳はハロスを見上げたまま動かない。
そこで初めて、ハロスはその違和感に気がついた。
かすれた声。
ハロスを見上げる目はどこか無表情で、しかしその目はうっすらと濡れていた。
「そんなことを言って騒ぎにでもなったら私の家の名誉に傷がつくかもしれないでしょう。そしたら大変よ。損をする人しかいないわ。誰も得をしない。
それなら黙ってる方が無難だわ。私が口を開いたって喜ぶ人なんていないもの」
機械的に流れる言葉は、まるでロボットが入力された文章を読み上げるかのように淡々としていて、感情の起伏を感じなかった。
虚ろな瞳はハロスを見上げたまま動かない。
そこで初めて、ハロスはその違和感に気がついた。