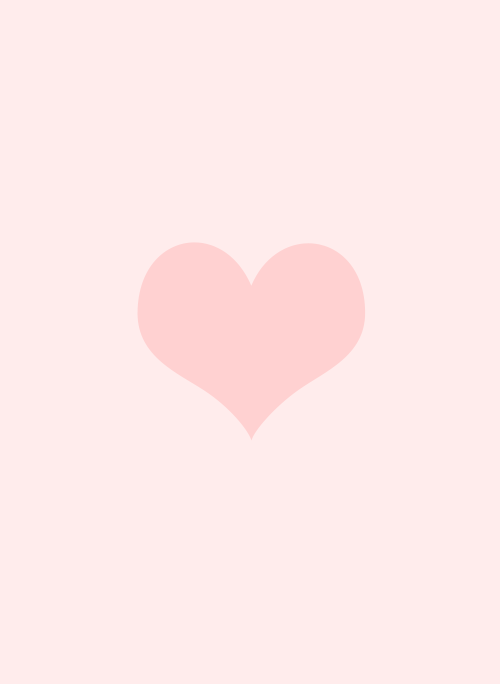すると、私達の前に影が掛かった。それも数人分の。その影を追って見上げると…
「わっ、皆!?」
そう。優香達が立っていた。口をあんぐり開けている。しかし、そんな様子もつかの間。三人はすぐにニヤニヤと笑って、凜華がこう言った。
「もうそろそろ閉園するから戻ってきたんだけど…
まだちょっと名残惜しいから、私達流れるプールで一周して来るね〜」
三人とも手をヒラヒラと振って退散していく。
み、見られた。
その一言に尽きる。私の頬がどんどん赤くなっていくのが分かった。
何もやましいことしてる訳じゃないのに…、何でこんなに恥ずかしいんだろ。
チラリと彼の顔を伺ってみる。
「!」
彼は口元に手を当て、少し俯いている。だけど、膝を触って少し下から覗いていた私には分かった。彼の染まった赤い頬。
胸が大きく音を立てた。そして、手汗が出てくる。
「え、えっと…もうそろそろ閉園、だよね。
さっき優香達も戻って来てたから、結城くんの友達も戻ってるかも。
私達もそろそろ別れた方がいいかな」
緊張する自分を誤魔化すように、早口でまくし立てた。
「あ、じゃあこれ…って、言っても濡れてるんだけど」
彼は膝に当てていた私のハンカチを差し出した。
「いやいや!それもう貰ってくれて良いよ!?古いから!」
水色がベースで右下にシャボン玉の刺繍がされたハンカチ。もう何年も前から使っているため、所々ほつれて糸が出て来ている。
それに何より…そのハンカチを返されると、一日中それを持ち歩き、寝る時も枕元に置く。と言うような変態行為をする自分が脳裏を掠めたからだ。
「マジで?
でも、ハンカチなんて結構大事な物じゃ…?」
私がそうは言っても、彼はやはり気が引けるようだった。気を使ってくれている人に無理強いをするのは私も気乗りしない。
「うーん…そっか。同じ学校とかなら今度あった時に返してもらえば良いんだけど…。しょうがないね」
変態コース決定か。と思いながら彼の持っているハンカチに手を伸ばそうとすると、彼はハンカチを自分の元に引き寄せた。
「?」
「いや、やっぱり俺貰っとくよ。これ」