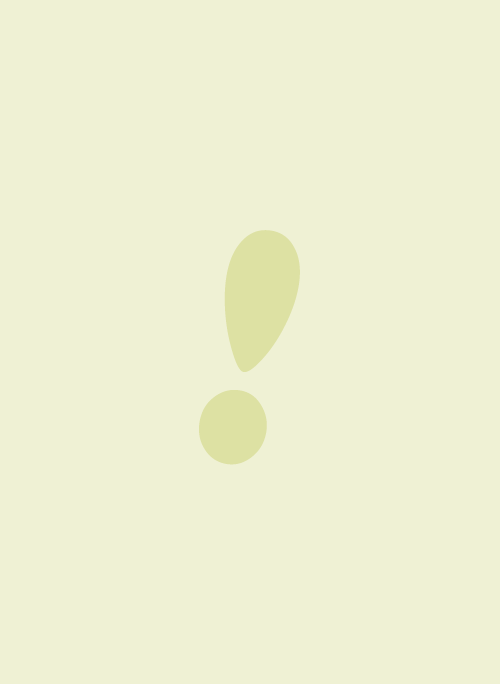その日は先客がいた。
いつもは俺だけの特等席であるはずのそこに誰かいるなんてことは初めてだったし、病棟の屋上で星見(ほしみ)をしようなんて物好きが自分の他にいるなんて考えもしなかった。
しかしそんなことよりも、俺は目の前の光景に心を奪われた。
闇色の空に散らばる星々。
皓々と輝く十六夜の月。
その冴えた光に照らされた、蒼皓い天使。
それは真っ白い入院着を羽織った少女の姿だったのだが。
長い黒髪と白い入院着が月明かりで蒼皓く輝いて見え、少女がまるで天の使いであるのように思えたのだ。
両腕を広げ、月の光を全身で浴びるように立つ少女の姿を目の当たりにした俺は、息を呑み、言葉を失い、まるで何かの呪縛に掛かったかのように声が出せなくなった。
その一方で、足は勝手に前に出て、少女の傍(かたわ)らへ向かって進んで行った。