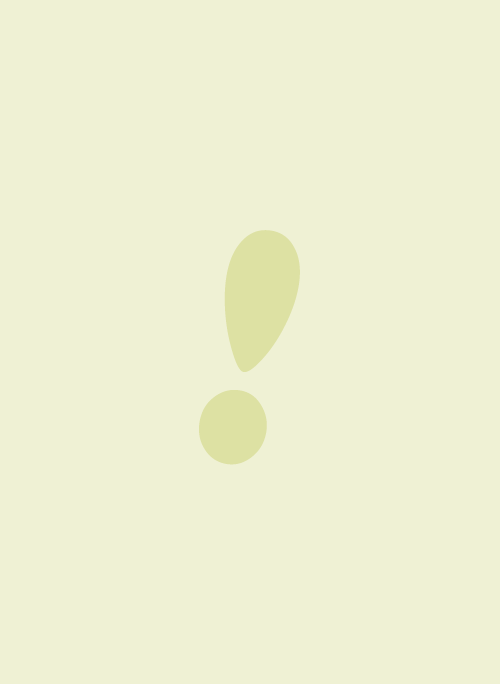「兎季矢さん、ですね?」
「え? ええ、そうです古瀬(ふるせ)兎季矢です」
「お待ちしていました」
名前を呼ばれて、やっと我に返った。女性は、黒髪をアップにし、白のシャツに黒のパンツ、濃紺のエプロンという制服をまとっている。見た目まだ十代後半かと思えるほど年若かったのだが、他に店員がいなかった様子から察するに、たぶん彼女が店長なのだろう。言葉を失って棒立ちの俺を、笑って迎え入れてくれた。
「初対面なのに、笑ってしまってごめんなさいね。あの子たちも最初ここに来たとき、お客様とおんなじ反応をしてたものだから、おかしくて」
「はあ」
照れたように笑って、どこかの女将さんのような口調で弁明する店長さんのなんとも言えない雰囲気に毒気を抜かれた俺は、せっかく引き締め直した気が霧散していくのを感じた。しかし不思議と悪い気はしなかった。それに加え、璃那たちがここを気に入っている理由がわかったような気がした。
「あの子たちなら、奥でお待ちかねよ。わたしはちょっと買い物で席を外すけど、ちょうど蒸らしていた香茶の葉がいい具合に起きるころだから、ぜひゆっくりしていってくださいね」
「あ、はい。ありがとうございます」
本当は五分とすら店内に居るつもりもなかったのだが、やんわりと、それでいて有無を言わさない感じで一方的に言われてしまい、うなずくことしか出来なかった。
店を出て行ってしまった店長さんにすっかり崩されてしまった調子をひと呼吸で整え、店の奥へ目を向けると。揃って私服姿の女性たちがテーブル席からこちらを見て、三者三様に手を振っていた。