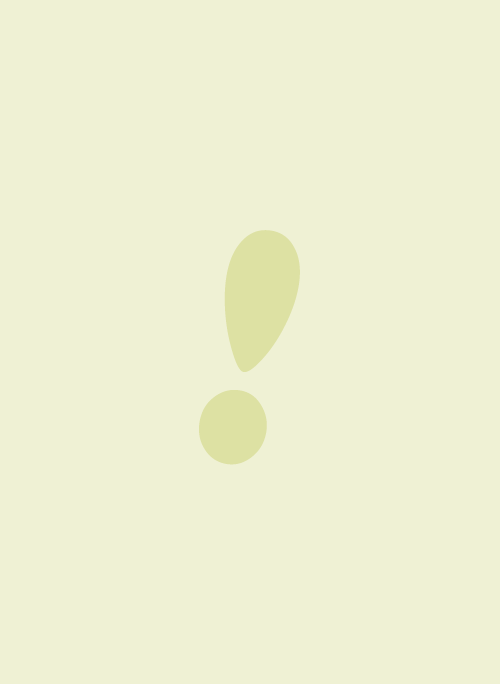仮に高卒で学生生活にピリオドを打つとしても、四年半はこの北の大地から出られない、出るわけにいかない。少なくとも、璃那が夢をつかむまでは会わない方がいいとまで、思い込んでいた。
「だから、先に行っててよ」
「…………」
「行ってらっしゃい、姉さん」
一切の私情を振り切るように精一杯の笑顔で告げると、璃那は驚いたように目を見開いて俺を見つめた。
てっきり俺に引き止めてもらえるものと思っていたからか、それとも逆に、予想していた通りの言葉だったからか。どんな思いが璃那の胸のうちにあったのか、それはわからない。
もちろん、その気になれば〝テレパス〟で知ることは出来たかもしれないが、そんな野暮なことはしようとも思わなかった。
やがて、璃那は瞳を潤ませたまま微笑み、滲んだ声で、しかしはっきりと言った。
「うん、行ってきます」
――これが、告白シーンの一部始終……なのだが。
こんなばかみたいで小っ恥ずかしい話、誰にも話せるわけがない。
しかもカッコつかないことに、結果的には、このときの誓いを守ることは出来なかった。
実際に璃那の近くに行けたのは誓いよりも一年遅く、六年が経ってからだったのだ。
六年後、今から二年前。