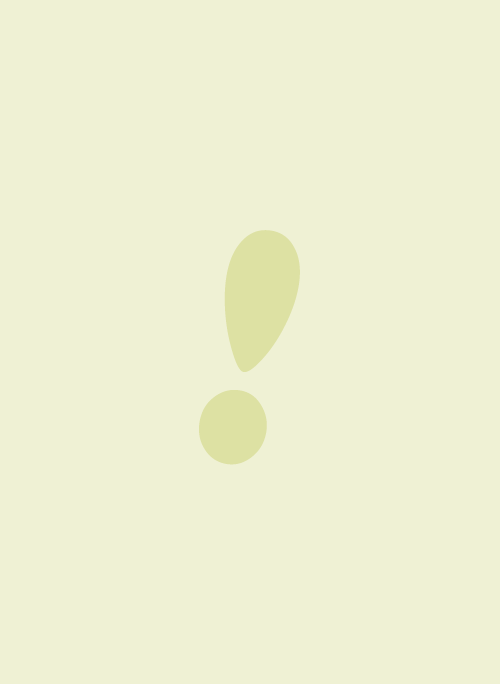璃那には、声優になるという夢があった。
当時はまだ、北海道からでは声優を目指すには遠過ぎた。
しかし、俺が告白した時点で璃那は、上京して夢を実現に近づけるチャンスを得ていた。
気持ちは嬉しい。けど上京すると、俺との距離が遠くなってしまう。今以上の遠距離は、恋人同士には辛すぎると彼女は思っていた。
だからこその『ありがとう。でもごめんなさい』だった。
昨夜の時点で、もしかしたら告白されるかもしれないと気付いていた璃那は、たくさん、たくさん悩んだって言っていた。
「でもね、思ったんだ。いまのままなら、いまより遠くなっても大丈夫かなって。
だから。
もうしばらくはいまのまま。トキくんの頼りない姉貴でいさせてくれないかな……。それじゃ、ダメ?」
上目遣いに、悲しみと辛さと期待と不安を綯い交ぜにしたような複雑な色を瞳に滲(にじ)ませて、たどたどしく話し、訊ねた。
その姿は、思い余って抱きしめてしまいたいくらい弱々しかったけれど、出来なかった。
このとき璃那は、まだ迷っていた。そして、俺の答えを怖がってもいた。そうでなければ、あんな表情にはならない。
夢と恋人。自分としてはどちらを選んで欲しいとか、どちらを選び取るのが璃那のために良いかなんて自問は愚問で。答えは、考えるまでもなかった。
「うん、ダメだね」
不満そうに言うと、璃那が『そう……だよね』とゆっくりうなだれるのが見えた。
そして、続けた。
「――なんて言うわけ、ないでしょ」
「え?」
精一杯の笑顔で前言を翻(ひるがえ)すと、璃那は弾かれたように顔を上げて、驚きに目を見張った。
「ルナ姉にとって声優になるって夢がどれだけ大切で大きいものか語るのをずっと聴いてた僕が、反対するとでも思った? 夢への切符と僕となんて、天秤にかけるまでもないじゃない」