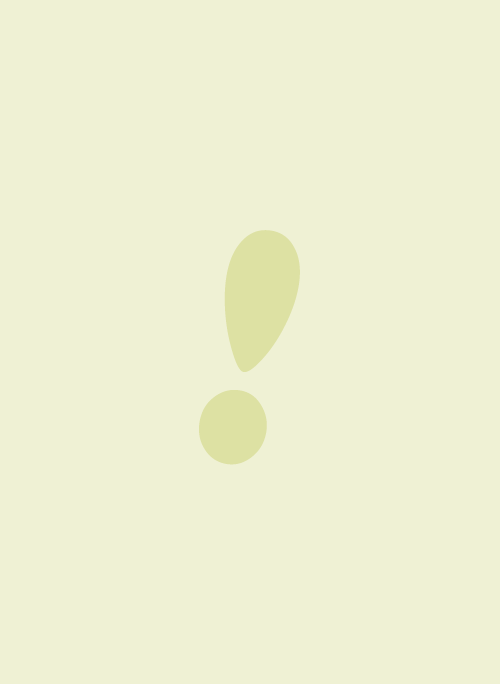二人は俺の脳に負担がかからないように気をつけながら、璃那とのことを思い出させようと頑張ってくれた。だが残念ながら、大した成果は上がらなかった。
一方で、手足の痺れを治すリハビリは成果が上がり、ひとりでも普通に生活が出来るようになるまで回復した。その時点で、俺は地元へ帰ったのだ。
それが、今から一年前のこと。
「あのあと、徐々に記憶を取り戻していったんです」
「そうなんだ……よかった。本当に」
悠紀は笑みを浮かべてそう言ったが、それはいつもの無邪気な少女のような笑みとは違い、母性のこもった、慈愛に満ちた微笑だった。
「でも、いつごろから?」
そう訊いてきたのは、璃那だった。
質問したいのはむしろ俺の方だったが、取り敢えず今は答える方に徹することにした。
「コイツがひょっこりウチに現れたころから、少しずつだよ」
「アルテが?」
「うん」
鳥かごの中の仔猫を指さすと、悠紀が俺の肩に手を置いた。
「ねえ兎季矢くん。ずっと気になってたんだけど、その子もしかして……」
「悠紀姉、アルテを知ってるんですか?」
「アルテっていうのね。名前は今日初めて知ったわ。でもたぶんその子、みゃーこ先生のところの猫じゃないかしら」
悠紀が『みゃーこ先生』と呼ぶ人物に、俺は心当たりがあった。