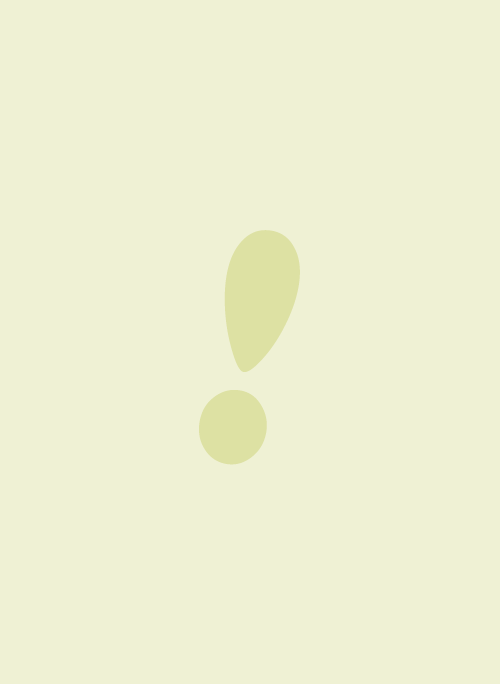「初恋の人との再会だっていうのに、ずいぶんと地味な恰好ね、トキ」
佐藤――もとい、麻宮三姉妹の末妹である蒼依は、初めて会ったときから俺を特別天然記念物呼ばわりしていた。
家族でもないのに馴れ馴れしいなと思ったら、次の瞬間「だったらいいじゃない、遅かれ早かれ家族になるんだから」と冷静に返され、何も言い返せなかった。
現在二十二歳。
悠紀とは四つ、璃那とは二つ、歳が離れている。
俺とは同い年だが、学年では俺の方がひとつ上。
璃那と比べるとだいぶ身長差があるし、スタイルも性格も、声も口調も似ても似つかない。
しかし遺伝子のいたずらか、容貌(ようぼう)が双子かと思うくらい璃那とそっくりで、もし二人のヘアスタイルやメイクを同じにされたら、顔だけではまるで区別がつかない。
月明かりで青みがかった黒髪のサイドテールを揺らしながら、俺たちと同じ高度まで降りてきた蒼依は、開口一番、初めて会ったときの第一声と同じことを言った。
「さっき璃那にも言われたよ。そういうお前は、ずいぶん派手な恰好をしてるじゃないか」
「そう?」
それは一見すると、典型的なメイド服のようだった。
だが、ワンピースタイプのエプロンドレスの色が濃紺ではなくサファイアのように深い青であることや、ヘッドドレスがないことから察すると、メイド服風なウェイトレスの制服なのかもしれない。
ただ、そのデザインが実用性や機能性よりも見せることを重視したものなのは、誰の目から見ても間違いないだろう。