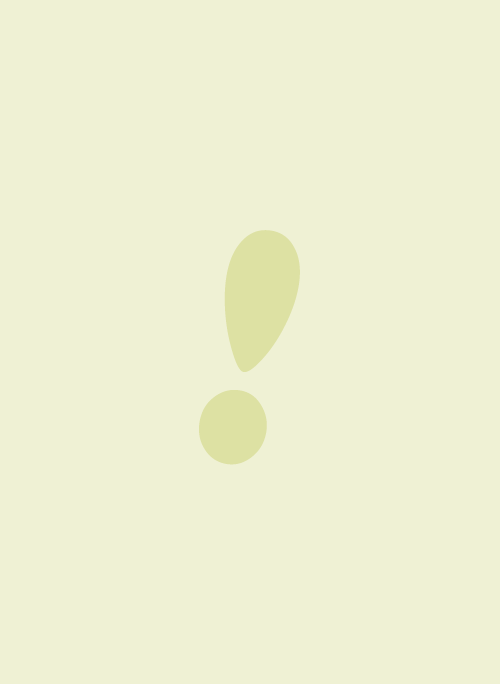そこまで一気に考えをめぐらせた俺は、この凄(すさ)まじい息苦しさをボディランゲージで伝えたいのを必死に抑え、努めて冷静に、別の手段で訴(うった)えることにした。
《…………苦しい》
「え?」
すると締めつけは、彼女の驚きとともにハグに変わった。
――というのは表現のあやで、実際には単に腕の力が緩んだだけに過ぎない。
《逢えて嬉しいのは痛いほどよくわかったよ。けど、それで窒息死させられちゃたまらない》
「ああっ、ごめん!」
冷静に
――なんでこんなに冷静なのか自分でもよくわからないが――
指摘すると、慌(あわ)てた声がしてから石鹸の香りが離れ、薄翠色の闇から解放された。
助かったと安堵する一方で、解放されて残念なようでもある。
複雑な思いが綯(な)い交ぜになったため息をついて顔を上げると、
「久しぶりだね、トキくん」
「――うん。本当に久しぶりだね、ルナ姉さん」
「ああ、なつかしいなあ、その呼び方」
彼女――璃那の微笑みは澄みきっていた。
様々な思いで混沌としていた俺の胸中とは、まるで対照的だった。
そういえば十三年前。
ルナこと佐藤璃那(りな)と初めて出逢ったころにも、薄翠色の闇に襲われたことがあった。