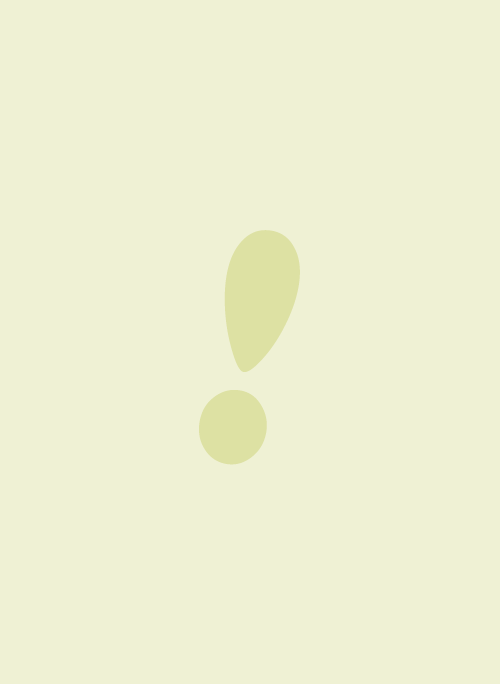真夏の星空の中
頭のない操り人形のような星座が
天頂にある
そこから放射状に長く短く
断続的に飛び交う流れ星――
ペルセウス座流星群を観るたびに
思い出すことがある
丘の上から
それを観ている父さんと俺
父さんは
流星よりも星空よりも
さらにその遠くを見つめていた
俺は
父さんの様子に気付かず
流星の群れに魅入っていた
不意に父さんは
俺の頭に手を乗せてこう言った
「俺はあと何回これを観ることが出来るか
わからない
お前には俺と同じ運命が待っている
その運命からお前を救うことは
俺には出来ない
その代わり
お前の進む道をいくらか延ばしてやることは
出来る
その間に
幸せな記憶をひとつでも多く残せよ」
しかし俺には
父さんがなぜそんな事を言ったのか
まるで意味がわからなかった
なぜ父さんの体が
死んだあともしばらくの間
父さんの友人である女性の病院に
検体として置かれていたのかも
何のためにそんなことをしていたのかも
だが
今ならわかる