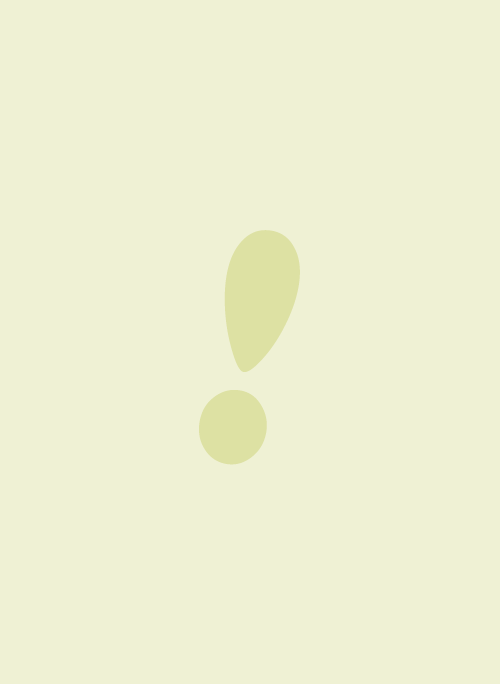「そうよ。女は男が幸せにしてやらなきゃならないなんて、男の自惚れだわ。それか思い上がり。男に幸せにしてもらわなきゃ幸せになれないほど、女はヤワじゃない。第一、このアタシや娘たちが、そんなヤワだと思う?」
「……いいえ」
朱海さんのことはよく知らないが、少なくとも、三姉妹は強い。もっと言えば、強い自分であろうとしている。そんな女性が、ヤワなわけはない。ならばその母親がヤワなわけがないとも思う。
「そうでしょう? もしそれが理由で二年前のあのときに今の話を璃那にしていたら、あの子は『わたしは幸せにしてもらわなきゃ幸せになれないような女じゃないよ』って言ったわよ。絶対にね」
「ええ、そうでしょうね」
朱海さんは、璃那の産みの親。誰よりも深く彼女を知っているだろう女性の見立てに、俺が異論を挟めるわけもない。
それに、俺が璃那を幸せにしなきゃいけないなんて思っていないのも確かだ。一方がもう一方を幸せにしなくてはいけないのではなく、二人で幸せになれるよう、ともに日々を積み重ねていくものだと思っている。
しかし……
「そうよ。なんなら明日、あの子に会ったら直接訊いてみたらいいわ。葬儀の日のことを話したら『それならそれで、あのときに言ってくれたらよかったのに』って言われるわよ。きっとね」
「はい。でも……」
「でも、何?」