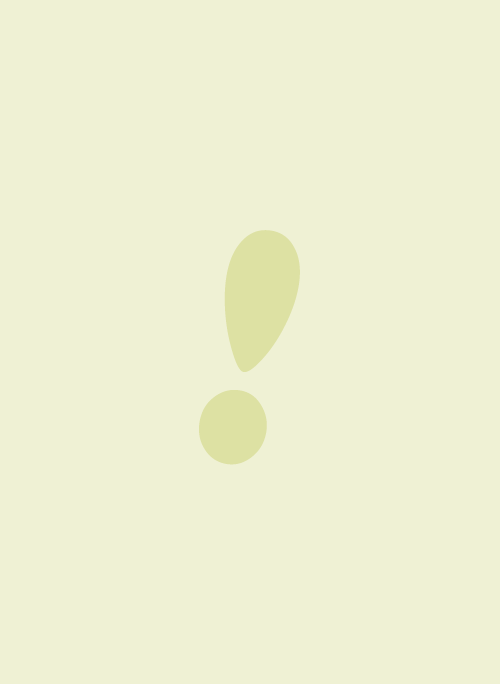やがて少女のすぐそばまで来ると足は止まったが、その間、俺の視線は片時も少女から離れず、近づくにつれて、少女が自分より背が高いのがわかった。
少女の髪は、絹のように艶(つや)やかで、腰まで届くほど長かった。
入院着の中には、薄翠(うすみどり)色のパジャマを着ていた。シルクのような光沢のある素材のシンプルなデザインは、子供心にも大人っぽさを感じさせた。
目をつむって空を仰ぐ少女の横顔は可愛いというよりも――
「……きれい」だった。
「そうだね」
思わずこぼれた呟(つぶや)きに返ってきたのは、風に揺れる風鈴のように凜(りん)とした、涼やかな声。
「え?」
「きれいって、キミが言ったから。キミもコレを見に来たんでしょ?」
驚くと、人懐っこい笑みを見せて、少女は欠け始めの月を指さす。
息を呑み、ふたたび呪縛に掛かった俺は、少女の誤解を指摘するのも忘れて、ただうなずいた。
「そっか、君も星を見るのが好きなんだね、わたしとおんなじ」
「…………」
間違いなく初対面のはずなのに、もうすでに仲良しのように接してくる少女に、俺は戸惑った。
「むぅ、無言? ねえひょっとしてキミ、今夜わたしが自分より先にここに来たことを怒ってる?」
視線の高さを俺と合わせるように膝(ひざ)を折り、小首を傾(かし)げて不安げに訊いてきた少女に、怒りのせいで喋(しゃべ)らないのではないことを伝えるために俺は、思いきり首を左右に振った。
「ほんと? ならよかった」