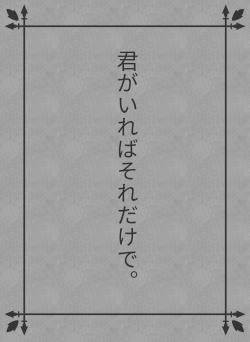「なぜそう言い切れるんだ。別の他人かもしれないんだぞ」
「いや。そいつを見て泣いたんならお前は俺の友、ラークペイだ。・・・仲間の形見なんだ、そいつ」
俺の肩に腕を回してペンダントを見つめるジンルークさんは、俺以上に切ない表情をしていた。仲間の形見か。それをラークペイさんが持っていたと言うんだろうな。俺が泣いたのはそのせいだというのだろうか。もしそうなら、ペンダントは俺が持っていなくてはいけないな。
「無関係の奴が絶望もしてないのに泣かないだろうよ」
「本当に良いのか?他人だったとしても」
「他人だったならこれから友になれば良いさ」
何て奴なんだ。そこまで信じられるのはどうしてなんだ。
「いや。そいつを見て泣いたんならお前は俺の友、ラークペイだ。・・・仲間の形見なんだ、そいつ」
俺の肩に腕を回してペンダントを見つめるジンルークさんは、俺以上に切ない表情をしていた。仲間の形見か。それをラークペイさんが持っていたと言うんだろうな。俺が泣いたのはそのせいだというのだろうか。もしそうなら、ペンダントは俺が持っていなくてはいけないな。
「無関係の奴が絶望もしてないのに泣かないだろうよ」
「本当に良いのか?他人だったとしても」
「他人だったならこれから友になれば良いさ」
何て奴なんだ。そこまで信じられるのはどうしてなんだ。