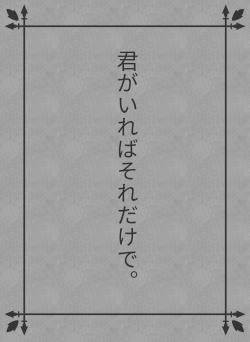ただ、ラークたちの優しさは非常にありがたいけれど周りに気を張っていなければ、また何かを失う気がした。その証拠に、先程から誰かに見られている気がしてならないんだ。
「あの」
「あぁ」
「・・・」
その事に関しては皆気付いているようだ。ただの医師として暮らしてきた私より、能力が長けていて当たり前なのかもしれない。でも、ちゃんと分かっているのか不安になるのも事実だろう。だって一番警戒しなくてはいけないはずの彼女が嫌というほど呑気なのだから。
「ねぇ、いいの?呼ばなくて」
隠れている何者かの気配を悟ってはいる彼女。でも、警戒心を持つ事もなく目の前に呼んでみてはと提案してくるのだ。
「あの」
「あぁ」
「・・・」
その事に関しては皆気付いているようだ。ただの医師として暮らしてきた私より、能力が長けていて当たり前なのかもしれない。でも、ちゃんと分かっているのか不安になるのも事実だろう。だって一番警戒しなくてはいけないはずの彼女が嫌というほど呑気なのだから。
「ねぇ、いいの?呼ばなくて」
隠れている何者かの気配を悟ってはいる彼女。でも、警戒心を持つ事もなく目の前に呼んでみてはと提案してくるのだ。