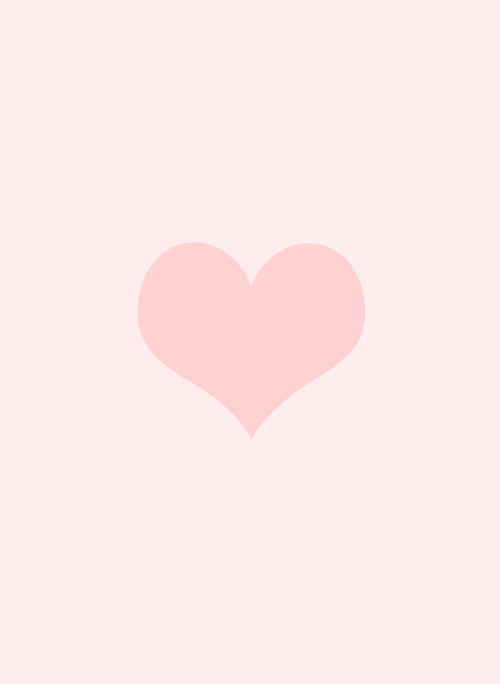「来週からは一般入試が控えているため、生徒は登校禁止です。くれぐれも間違えて学校に来たりしないように」
銀縁メガネを掛けた担任がそう言った。
そんな話を聞きながら、俺はペンを回してテストが終わった解放感を味わっていた。
何度もそれを繰り返していると、ペンがバランスを崩して床に落ちた。俺はそれを拾い際、ある人物に目を向けた。
───日野楓子。
彼女は入学した当時、隣の席だった。女子では珍しい「隠れ家カグラ」が好きな子で、大いにその作品で盛り上がった事もある。
そんな彼女から先日、テスト期間に入る前のバレンタインデーで飴をもらった。あれが、俺にはまだ理解出来ないでいる。
彼女は何故「バレンタインデー」に飴を渡したのか。それともコンビニにあった飴を、同志の俺と共有したかった日がたまたま「バレンタインデー」だったのか。分からない。
だが、俺はそれ以上に気になっていることがあった。
あの日、彼女から飴を貰ったのは俺が失恋した日だ。改札口で人は居なかったものの、ある意味公開告白をして見事に振られた。
それが、彼女に聴こえていた可能性がある。聴こえていたからと言ってどう、と言う訳では無いが、もし彼女が聞いていたなら、俺と同じように悲しい思いになっていなかったか気になるのだ。
また入学当時に戻ると、彼女と「隠れ家カグラ」で盛り上がったときに、彼女は感受性が強いことが分かった。どのシーンで泣いたとかをよく言っていたので「泣き虫だなぁ」と突っ込んだのを覚えている。
そしたら、彼女は「友達の悲しい話だけでも泣いたりする」と照れながらも笑いにして言っていた。
もし彼女が俺の一部始終を見ていたのだとしたら、感化された彼女は気を使って飴をくれたのかもしれない。自分の好きな物までを犠牲にして。
そんなたくさんの可能性がバレンタイン以降ずっと俺の頭を占めていて、最近は日野さんへの申し訳ない気持ちがどんどん膨れ上がっている。
…しかし、いつまでも可能性の話をしていても埒が明かない。
「起立」
号令に従って俺は立ち上がった。
「はいでは、さようなら」
担任の声と同時にクラスメイトがぞろぞろと教室を出ていく。その中で、俺は人を避けながら彼女の元へ向かった。
「日野さん」
彼女は少し肩を跳ねさせたあと、恐る恐るこちらを見た。
「ど、どうしたの?山崎くん…」
あれ、日野さんてこんなに目大きかったっけ。
薄い唇に、少しくせ毛の黒髪。二重ではないけどくりくりした瞳に長いまつげ。
これは…。
入学式以来、ちゃんと対面してみて分かった事。日野さんは俺が思っていたよりずっと、可愛い子だった。
何だか目を合わせるのが恥ずかしくなって、俺は斜め上を見た。
「バレンタインの日の事で…聞きたいことがあるんだけど、良いかな」
To be continued in whiteday…?