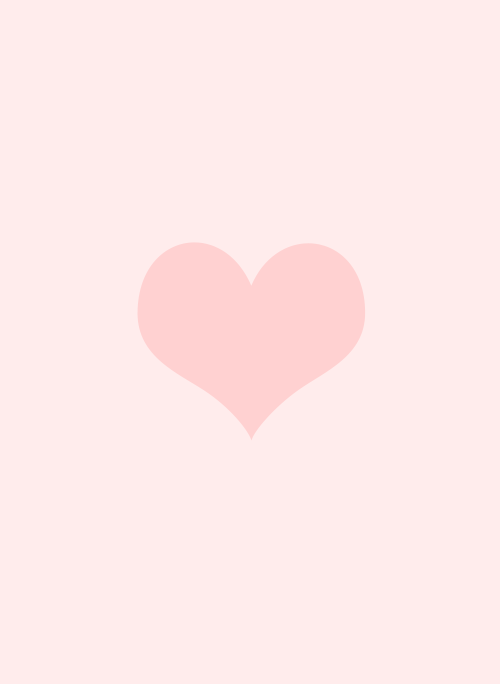「わっ、日野さん?ビックリした…。
珍しいね、こんな遅い時間に居るなんて」
階段を上がったところですぐに立っていた私に驚いた山崎くん。いつもと比べて元気がないのは一目瞭然だ。
「うん。山崎くん待ってた」
すっごく長い間ね。
「え、俺?」
彼は面食らった顔をする。
「うん。渡したい物があって…。
手、出してくれる?」
山崎くんは怪訝そうな顔をしながらも右手を出した。
「あ、両手」
私に言われるまま左手も揃えた山崎くん。ますます怪訝そうな顔をしている。その上に、私はあるものを落とした。
ばらばら。
山崎くんの手には小さな袋がたくさん溢れる。
「えっ、わわ」
零れるそれを、山崎くんは必死にキャッチする。自分の手の中に収まると、彼はそれが何か気づいたようだった。
「え、これもしかして…」
彼は顔を上げて私を見る。
「あげる。「隠れ家カグラ」の飴。
コンビニで売ってたから」
これが、今の私の精一杯。バレンタインという特別な日に渡すチョコレートでも何でもなくて、ただ同志の間のちょっとしたプレゼント。
私は精一杯の笑顔を作って言った。
「好きだったよね。隠れ家カグラ」
彼は目を瞬かせながら「うん」と頷いた。
どうしていきなりこんなものを渡されたのか、分かってないんだろうな。目がまんまるだ。
そんな彼の様子も愛しくて、だけど苦しくて…目頭が熱くなってくる。
「じゃあ、また…ね」
彼と同じ空間に居られるのも限界になって、階段を駆け下りた。
ごめん、麻衣。私、渡せなかった。
トイレに駆け込むと堰が切れて、私の目からは滝のように涙が流れた。