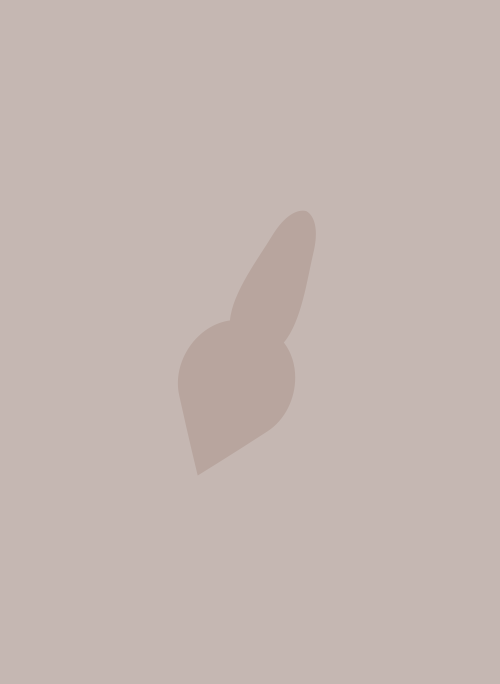夢から覚めた。
「先生?」
放課後、合唱部と部活動をしている時だ。
ぼーっとしていたらしい。部員の一人に起こされた。ピアノの上で寝てしまうなんて自分らしくない。
「大切なことを思い出したんだよ」
彼女に笑いかける。出来るだけピアノらしくなるように静かに目を細めて。
「なんですか」
僕はジャケットのポケットから御守りを取り出す。物心ついたときから側にいた品だ。祖母がくれたものじゃないかと母さえも出所のわからなかった古びた御守り。気味悪くなることなく安心感さえあるので、成人してもなお手放すことはない。
まさか、君たちだったなんて。
「ごめん。ちょっと休憩にしようか。」
部員たちに休憩を促して、その隙にオレンジ色の御守りを覗く。
色褪せた写真が一枚入っていて、そこには懐かしい顔ぶれが揃っていた。
馬鹿だなあ。栞はこれを託したかったんだ。僕を残しておきたかったんだ。自分たちを残しておきたかったんだ。忘れたくない、そんな誰かの想いを汲んで。
今になって僕は思う。
僕があの学校で楽しく過ごすことでそれが成仏なんてのに繋がったんじゃないかと。だから、皆いなくなったのかなって。
新しい音楽室はあのときいなかった女子生徒のお喋りで埋まる。流行りの俳優や洋服のことだったり、明日のテストのことだったり。他愛もない会話。それが今は僕の人生で、音楽教諭になった僕は前よりピアノも上手くなっている。
机は音階の描かれた勤勉的なものへ変わって、まっさらなカーテン。整った譜面台や楽譜。穴の空いた壁。変わってくものや変わらないもの。全部を受諾できるようになった。
それはあの頃の僕ではなくなるというこであり、生まれ変わるってことだと思う。
もう一度、写真をよく見る。
真ん中に僕がいて、その隣に君がいた。
歪な顔で真っ直ぐ笑っていた。
さようなら、だ。